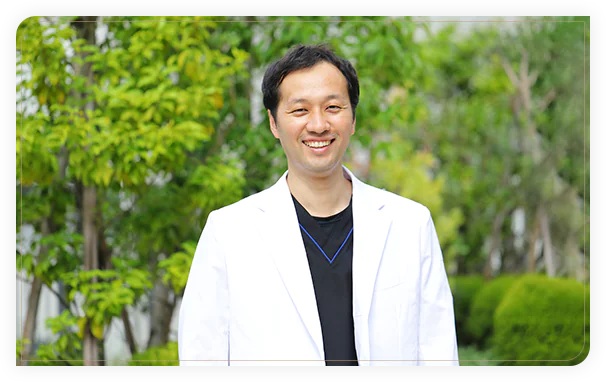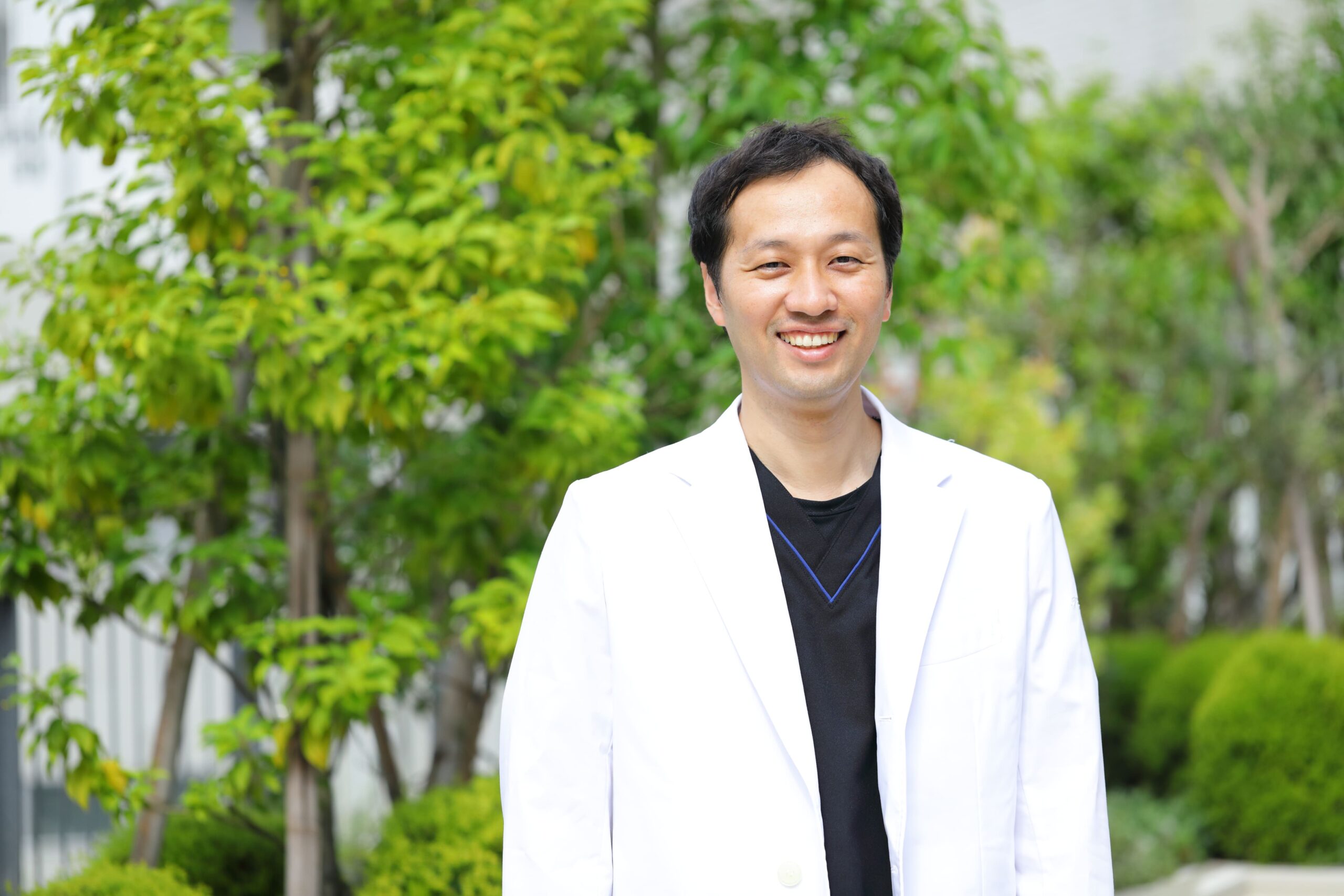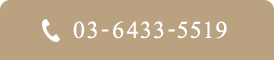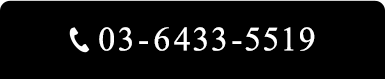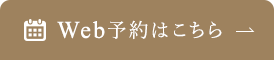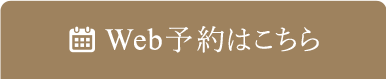避妊方法として広く知られている低容量ピルですが、その具体的な仕組みや効果について詳しく理解している女性は意外に少ないのが現状です。
低容量ピルは正しく服用することで高い避妊効果が期待できる一方で、服用方法や注意点を理解せずに使用すると、期待した効果が得られない場合があります。
本記事では、低容量ピルによる避妊の仕組みから他の避妊方法との比較、服用時の注意点まで詳しく解説します。
避妊を目的とした低容量ピルの使用を検討している方は、正しい知識を身につけて安全かつ効果的に活用していただくための参考にしてください。
■関連ページ
低用量ピルとは
低用量ピルは、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲスチン)の2つの女性ホルモンを含有した経口避妊薬です。
これらのホルモンは、体内で自然に分泌されるよりも少ない量で配合されており、そのため「低用量」と呼ばれています。
【関連記事】ピルの飲み始めはいつがいい?種類や効果が出るまでの期間を解説
低用量ピルの特徴
低用量ピルは、従来の中用量ピルと比較してホルモン含有量が少ないため、副作用が軽減されています。
そのため、長期間の継続使用が可能で、避妊効果に加え、月経に伴うさまざまな症状の改善も見込めます。
種類について
低用量ピルには、含有されるプロゲスチンの種類によって第1世代から第4世代まで分類されています。
それぞれ特徴が異なり、個人の体質や目的に応じて選択されます。
また、低用量ピルには、1周期中のホルモン量が一定の「1相性」と、自然な月経周期に近づけるためホルモン量が段階的に変化する「段階型」があります。
処方について
低用量ピルは医師の処方が必要な処方薬です。
初回処方時には、血液検査や血圧測定などの検査が行われることがあります。
また、定期的な検査とフォローアップが推奨されています。
低用量ピルの使用を検討する際は、医師と十分に相談し、自分に適した種類を選択しましょう。
関連記事:ピルは薬局で買える?購入できる場所とメリット・注意点について
低用量ピルによる避妊効果の仕組み
低用量ピルは、複数の仕組みによって避妊効果を発揮します。
これらの仕組みが同時に働くことで、高い避妊効果が得られます。
排卵を抑制する
低用量ピルの最も重要な避妊効果は、排卵の抑制です。
低用量ピルに含まれるエストロゲンとプロゲスチンが、脳の視床下部と下垂体に作用します。
これにより、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)の分泌が抑制され、卵胞の発育と排卵が阻害されます。
正しく服用すれば、排卵抑制効果は非常に高く、ほぼ確実に排卵を防げます。
排卵抑制効果を維持するためには、継続的な服用が必要です。
服用を中断すると、すぐに排卵機能が回復する可能性があります。
受精卵の子宮内膜への着床を阻止する
低用量ピルは、子宮内膜の状態を変化させることで着床を阻害します。
プロゲスチンの作用により、子宮内膜の増殖が抑制されます。
仮に受精が起こったとしても、受精卵が子宮内膜に着床しにくい状態になるでしょう。
低用量ピルを継続服用することで、子宮内膜は薄い状態に保たれます。
この状態では、受精卵の着床に必要な環境が整わないため、妊娠が成立しにくくなります。
精子の子宮内への侵入を阻止する
低用量ピルは、子宮頸管粘液の性状を変化させることで精子の侵入を阻害します。
プロゲスチンの作用により、子宮頸管粘液の粘稠度が高くなり、精子が子宮内に侵入することが困難になります。
変化した頸管粘液は物理的なバリアとなり、精子の通過を防ぎます。
これら3つの仕組みが同時に作用することで、低用量ピルは99%以上の避妊効果を発揮します。
ただし、この効果は正しい服用方法を守ることが前提となります。
低用量ピル以外の避妊方法とその効果
避妊方法には様々な選択肢があり、それぞれに特徴があります。
低用量ピルと他の避妊方法を比較することで、自分に適した方法が選択できます。
アフターピル
アフターピルは、緊急避妊薬とも呼ばれ、性交後に服用する避妊薬です。
避妊に失敗した場合や、避妊せずに性交を行った場合の緊急避妊法として使用されます。
排卵を遅らせることで避妊効果を発揮しますが、既に排卵が起こっている場合は効果が期待できません。
性交後72時間以内に服用することで、約85%の避妊効果が期待できます。
ただし、服用が早いほど効果が高くなります。
関連記事:ピルとアフターピルの違いとは?適切な使い分け方と注意点について
コンドーム
コンドームは最も一般的な避妊方法です。
正しく使用した場合の避妊効果は約98%とされています。
ただし、実際の使用では85%程度の効果だといわれています。
性感染症の予防効果があること、処方が不要であること、副作用がないことなどがメリットです。
一方で、使用方法によって効果に差が生じることや、性交時の感覚に影響する場合がある点はデメリットです。
IUS
IUS(子宮内器具)は、子宮内に挿入して使用します。
銅付加IUDと、レボノルゲストレル放出IUS(ミレーナ)があり、どちらも99%以上の高い避妊効果が期待できるでしょう。
長期間の避妊効果があり、服薬が不要、授乳中でも使用可能な点がメリットです。
ただし、挿入時に痛みを感じる場合がある、不正出血や感染症のリスクがある点はデメリットです。
基本的に出産経験のある女性に適していますが、未産婦でも使用可能な場合があります。
これらの避妊方法はそれぞれ特徴が異なるため、生活習慣や健康状態に応じて適した方法を選択することが大切です。
関連記事:ミレーナとは?効果や挿入するメリット・デメリット、副作用を解説
避妊目的で低用量ピルを服用する際の注意点
低用量ピルを避妊目的で使用する際は、以下の注意点を理解し、適切に対応することが重要です。
副作用がある
低用量ピルには、様々な副作用が起こる可能性があります。
吐き気や嘔吐、頭痛、乳房の張り、体重増加、不正出血などが表れやすい副作用です。
これらの副作用は、服用開始から数か月以内に軽減することが多いですが、症状が続く場合は医師に相談してください。
関連記事:ピルの副作用として起こり得る5つの症状とがん・血栓症へのリスク
血栓症のリスクが上昇する
低用量ピルの服用により、血栓症のリスクが上昇することが知られています。
血栓症は、血管内に血栓ができることで、肺塞栓症や脳梗塞などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
以下の要因がある場合は、血栓症のリスクが高くなります。
- 喫煙
- 35歳以上
- 肥満
- 長期間の安静
- 血栓症の既往歴または家族歴
予防するためには、禁煙をする、適度な運動をする、水分を多めに摂取する、長時間の座位を避けるなどの方法があります。
飲み忘れる可能性がある
低用量ピルは毎日の服用が必要で、飲み忘れは避妊効果を低下させます。
1日の飲み忘れでも、避妊効果が低下する可能性があります。
2日以上になると、避妊効果は大幅に低下するでしょう。
避妊を目的としていた場合、本来の効果が得られなくなってしまいます。
飲み忘れを防ぐためには、アラームの活用や服薬カレンダーの使用が有効です。また、毎日決められた時間に飲むようにして、習慣化することも大切です。
飲み忘れた場合は、1日の飲み忘れであれば直ちに服用し、次の錠剤は予定通り服用します。
ただし、飲み忘れの期間によって対応が異なるため、医師の指示を仰ぎましょう。
関連記事:低容量ピルを飲み忘れた時はどうする?対処法やリスクを解説
性感染症は防げない
低用量ピルには、HIVやクラミジア、ヘルペスなどの性感染症を予防する効果はありません。
性感染症を予防するためには、コンドームの併用が効果的です。低用量ピルと併用することで、避妊と感染症予防の両方に対応できます。
これらの注意点を理解し、適した対応をしながら、低用量ピルを安全かつ効果的に使用しましょう。
低用量ピルは正しく服用すると高い避妊効果が期待できる
低用量ピルは、排卵抑制、着床阻害、精子侵入阻止の3つの仕組みにより、正しい方法で服用を続ければ、99%以上の避妊効果が得られます。
他の避妊方法と比較しても優れた効果を示しますが、性感染症の予防効果はないため、必要に応じてコンドームとの併用を検討することが重要です。
服用にあたっては、副作用や血栓症のリスク、飲み忘れに注意しなくてはなりません。
特に血栓症は重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、リスク要因を理解し、適切な予防策を講じましょう。
低用量ピルを使用する際は、医師と十分に相談し、自分に適した種類を選択することが重要です。
渋谷・原宿・明治神宮前・表参道の婦人科・産婦人科 - LOG原宿
診察のご予約はこちら


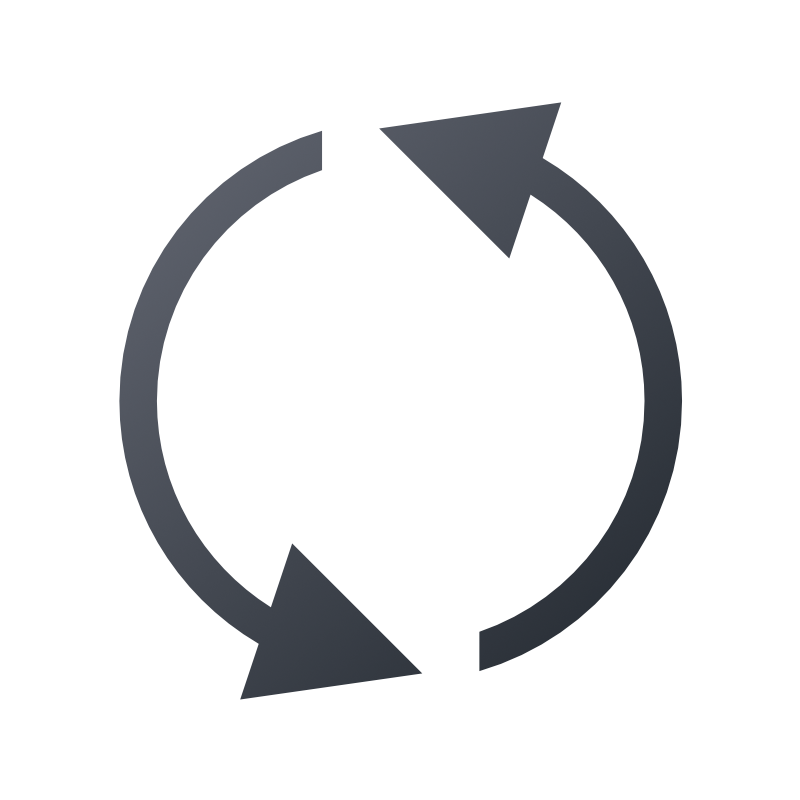 2025.12.23
2025.12.23