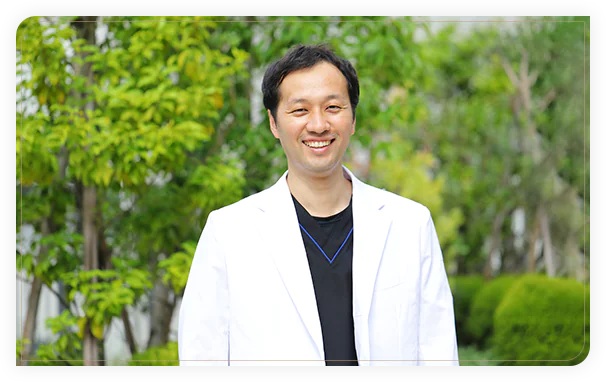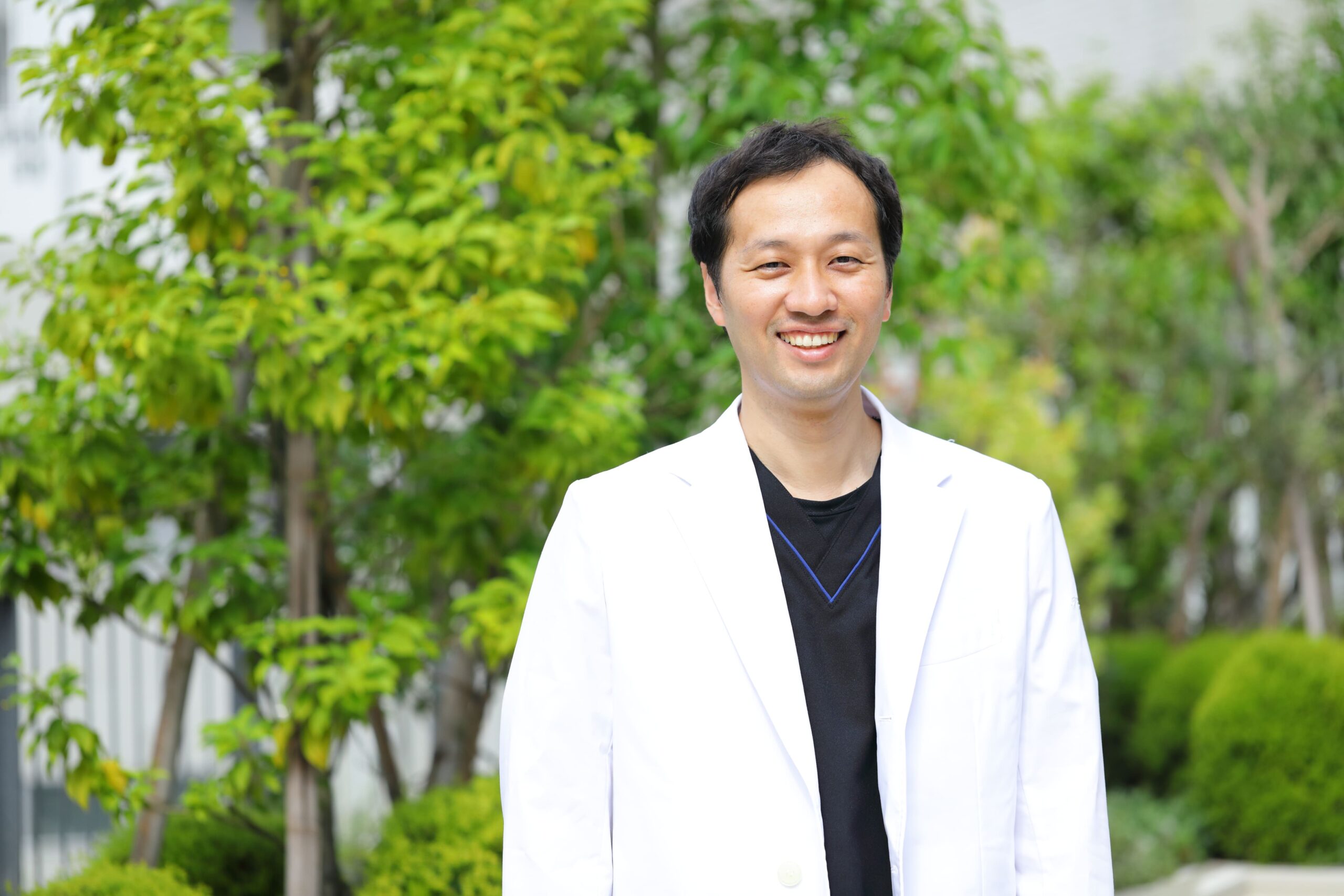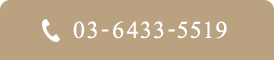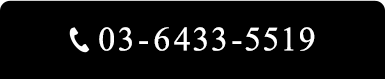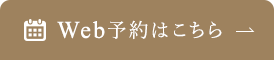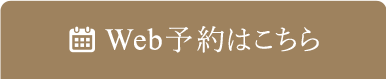おりものは、女性の健康状態を知る重要なサインです。
正常なおりものは透明から乳白色で、においもほとんどありません。
しかし、色や量、においに変化が現れた場合は、感染症や婦人科疾患の可能性があります。
本記事では、おりものの基本的な知識から、異常がある時の色やにおいの原因、適したケア方法まで詳しく解説します。
おりものの変化を正しく理解し、早期発見・早期治療につなげましょう。
■関連ページ
おりものとは?
おりものは、女性の膣や子宮頸管、子宮内膜から分泌される分泌物の総称です。
医学的には「帯下」と呼ばれ、女性の生殖器官の健康を維持する重要な役割を果たしています。
おりものの主な成分は、膣壁から分泌される粘液、子宮頸管から分泌される粘液、そして剥がれ落ちた膣や子宮の細胞です。
これらが混合することで、透明から白っぽい色の分泌物になります。
正常なおりものの重要な機能は、膣内の自浄作用です。
おりものには善玉菌である乳酸菌が含まれており、これが膣内のpHを酸性に保ちます。
酸性環境は、病原菌の繁殖を抑制し、感染症から体を守る重要な防御機能を果たしています。
また、おりものは膣の潤滑作用も担っています。適度な湿度を保つことで、膣壁の乾燥を防ぎ、細菌の侵入を防ぐバリア機能を維持しているのです。
おりものの量や性状は、女性ホルモンの影響を大きく受けます。そのため、月経周期や年齢、妊娠の有無などによって変化することは正常な現象です。
個人差はありますが、健康な女性であれば、1日に1〜2ml程度、ティースプーン半分程度の量のおりものが分泌されます。
おりものの観察は、健康状態を把握する大切な手段です。色やにおい、量、性状の変化を観察することで、体の異常を早期に発見できます。
異常がある時のおりものの色
おりものの色の変化は、様々な疾患や感染症のサインである可能性があります。
色別にその原因と特徴を詳しく解説します。
黄色・黄緑色のおりもの
黄色や黄緑色のおりものは、細菌感染症の可能性が高いサインです。
特に、膣トリコモナス症や淋菌感染症、細菌性膣症などが原因となることが多く見られます。
膣トリコモナス症
おりものは黄緑色で泡状になり、強い悪臭を伴います。
また、外陰部のかゆみや痛み、排尿時の痛みなどの症状も現れることがあります。
淋菌感染症
黄色から黄緑色のおりものが増加し、膿のような性状を示します。
下腹部痛や発熱を伴うこともあります。
細菌性膣症
黄色いおりものと魚のような特徴的なにおいが現れます。
茶色のおりもの
茶色のおりものは、多くの場合、血液が混じることで生じます。
月経前後に見られる茶色いおりものは、月経血が少量ずつ排出されることによるもので、正常な生理現象です。特に心配する必要はありません。
ただし、月経時期以外に継続して茶色いおりものが続く場合は注意が必要です。
不正出血による茶色いおりものの場合、子宮頸管ポリープや子宮内膜症、子宮筋腫などの疾患が原因となることがあります。
また、子宮頸がんの初期症状として現れることもあるため、月経時期以外の茶色いおりものが続く場合は、婦人科を受診することが重要です。
また、着床出血でも茶色いおりものが見られることがあります。
受精卵が子宮内膜に着床する際の出血が原因で、通常は数日で止まります。
白色のおりもの
白色のおりものは、正常な場合もあれば、疾患のサインである場合もあります。
性状や伴う症状によって判断することが重要です。
正常な白色のおりものは、乳白色で粘性があり、においはほとんどありません。
月経周期の中でも、特に排卵前後に見られることが多く、これは正常な生理現象です。
ただし、以下のような疾患の可能性もあるため、十分に注意しましょう。
膣カンジダ症
白色のおりものはカッテージチーズのような白い塊状になります。
強いかゆみを伴うことが特徴で、外陰部の腫れや痛みも現れることがあります。
関連記事:カンジダ症の症状とは?原因・対処法・再発予防法について
細菌性膣症
白色のおりものが見られるのとともに、魚のような特徴的なにおいを伴います。
ピンク・その他のおりもの
ピンク色のおりものは、少量の血液が混じることで生じます。
排卵期の排卵出血や、月経前後の出血が原因となることが多く見られるでしょう。
排卵期のピンク色のおりものは、排卵に伴う卵胞の破裂により少量の出血が起こることで生じます。
これは正常な生理現象であり、通常は1-2日で止まります。
基礎体温の変化や軽い下腹部痛を伴うことがあります。
月経前後のピンク色のおりものも、正常な範囲内とされています。
月経開始前や終了後に見られることが多く、月経血が少量ずつ排出されることで起こります。
しかし、月経時期以外に継続してピンク色のおりものが見られる場合は、不正出血の可能性があるため、注意しなくてはなりません。
子宮頸管ポリープや子宮内膜症、ホルモンバランスの乱れなどが原因となることがあります。
月経周期とおりものの関係
おりものは、月経周期による女性ホルモンの変動に伴って、量や性状が変化します。
月経周期とおりものの関係を理解して、自身の健康状態を把握しましょう。
生理直後から卵胞期
月経終了直後から排卵前までの期間を卵胞期と呼びます。
この時期のおりものは比較的少量で、さらっとした性状を示します。
卵胞期前期は、月経終了後におりものの量が少なくなる時期です。
色は透明から薄い白色で、さらっとした性状を示します。
この時期は卵胞刺激ホルモン(FSH)の働きで卵胞が発育を始めますが、エストロゲンの分泌はまだ少なく、おりものの量も控えめです。
卵胞期後期になると、卵胞の発育に伴いエストロゲンの分泌が増加します。
おりものの量も徐々に増加し、やや粘性のある状態になります。
色は透明から乳白色で、においはほとんどありません。
卵胞期のおりものは、膣内の自浄作用を維持する重要な役割を果たしています。
適度な酸性度を保つことで、有害な細菌の増殖を防いでいます。
排卵期
排卵期は、月経周期の中でおりものの量が最も多くなる時期です。
精子の通過を助ける役割を担っています。
排卵期のおりものは、透明で粘性が高く、伸びの良い性状を示します。
指で伸ばすと10cm以上伸びることもあり、これは精子の子宮内への移動を助けるための自然な変化です。
この状態のおりものは「頸管粘液」と呼ばれ、精子にとって最適な環境を提供します。
量は個人差がありますが、通常の2~3倍程度に増加することが一般的です。
色は透明から薄い白色で、においはほとんどありません。
この時期のおりものは「卵白のような性状」とよく表現されます。
排卵期の特徴的なおりものは、排卵のタイミングを知る重要な指標となります。
基礎体温法と併用することで、より正確な排卵日の予測が可能になるでしょう。
黄体期
排卵後から次の月経開始までの期間を黄体期と呼びます。
この時期のおりものは、プロゲステロンの影響により粘性が高くなり、量は減少します。
黄体期前期では、排卵後にプロゲステロンの分泌が増加します。
この影響で、おりものの量は排卵期より減少し、粘性が高くなるのが一般的です。
色は白色から薄い黄色で、やや濁った状態になることがあります。
黄体期後期には、プロゲステロンの分泌がさらに増え、おりものの量は一層減少します。
この時期のおりものは、膣内を保護し、外部からの感染を防ぐ役割を担います。
その後、月経直前になると、ホルモンバランスの変化により、おりものに少量の血液が混じることがあります。
血が混じると不安を感じるかもしれませんが、正常な現象であり、月経開始の兆候による変化です。
月経期
月経期間中は、子宮内膜が剥離し、月経血として排出されます。
月経血と混合するため、通常のおりものとは異なる性状です。
月経初期は月経血の量が多く、おりものの性状はわかりにくくなります。
それでも、膣内の自浄作用は働き続け、感染症予防に役立っています。
月経後期になると、月経血の量が減少し、通常のおりものが確認できるようになります。
この時期のおりものは、月経血が少量混じることで、薄い茶色やピンク色を示すことがあるでしょう。
診察のご予約はこちら
おりものの性状による異常
おりものの性状の変化は、様々な疾患や感染症のサインである可能性があります。
正常な状態との違いを理解し、異常を早期に発見することが重要です。
- 量が多い
- ベタベタしている
- 水っぽくサラサラしている
- 白い塊が混ざっている
- においがきつい
量が多い
おりものの量が普段より明らかに多い場合は、感染症やホルモンバランスの乱れが原因である可能性があります。
感染症による量の増加は、細菌性膣症や膣トリコモナス症、カンジダ症などが原因となることが多いです。
これらの疾患では、おりものの量の増加とともに、色やにおいの変化、かゆみなどの症状も現れることが一般的です。
ホルモンバランスの乱れによる量の増加は、ストレスや生活習慣の変化、更年期の始まりなどが原因となることがあります。
特に更年期では、エストロゲンの分泌が不安定になることで、おりものの量が一時的に増加することがあります。
子宮頸管ポリープや子宮内膜症などの疾患でも、おりものの量が増加することがあります。
これらの場合、不正出血を伴うことが多く、医師の診察が必要です。
ベタベタしている
おりものがベタベタした粘性の高い状態になる場合は、感染症やホルモンバランスの変化が原因である可能性があります。
正常な排卵期のおりものも粘性が高くなる時期はありますが、透明で伸びが良く、においはほとんどありません。
しかし、感染症による粘性の増加では、色の変化や悪臭を伴うことが特徴です。
カンジダ症では、白色でカッテージチーズのような塊状のおりものが特徴的です。
強いかゆみを伴うことが多く、外陰部の腫れや痛みも現れることがあります。
細菌性膣症では、グレーがかった色でベタベタしたおりものが見られます。
魚のような特徴的なにおいを伴うことが多く、膣内のpHバランスの乱れが原因となります。
水っぽくサラサラしている
おりものが異常に水っぽくサラサラしている場合は、感染症やホルモンバランスの変化が原因である可能性があります。
正常な卵胞期のおりものもサラサラしていますが、この場合は量も適度で、色も透明から薄い白色です。
しかし、感染症による場合は、量の異常な増加や色の変化を伴うことが特徴です。
膣トリコモナス症では、黄緑色で泡状のおりものが特徴的です。
強い悪臭を伴い、外陰部のかゆみや痛みも現れることがあります。
細菌感染症では、水っぽいおりものとともに、色の変化や悪臭が現れることがあります。
特に膣内の常在菌バランスが崩れることで、このような症状が現れることがあります。
白い塊が混ざっている
おりものに白い塊が混ざっている場合は、主にカンジダ症が原因である可能性が高いです。
おりものはカッテージチーズやヨーグルトのような白い塊状となり、強いかゆみを伴うことが特徴です。
正常なおりものにも白い塊が混じることがありますが、この場合はかゆみなどの症状はなく、量も適度です。
症状を伴う場合は、医師の診察を受けることが重要です。
においがきつい
おりものの強いにおいは、感染症のサインである可能性が高いです。
正常なおりものは無臭かわずかに酸っぱいにおいがする程度です。
魚のような悪臭は、細菌性膣症の特徴的な症状です。
膣内のpHバランスが崩れることで、嫌気性菌が増殖し、このような特徴的なにおいが発生します。
膣トリコモナス症では、強い悪臭を伴う黄緑色のおりものが特徴的です。
この疾患は性感染症の一つで、パートナーとの同時治療が必要です。
腐敗臭のような強いにおいは、タンポンの取り忘れなど、異物が膣内に留まることによって発生する場合があります。
この場合は、速やかに医師の診察を受ける必要があります。
甘酸っぱいにおいは、糖尿病が原因となる場合もあります。
血糖値の上昇により、おりものの糖分が増加し、このようなにおいが発生することがあります。
診察のご予約はこちら
おりものに異常が出る病気の種類
おりものの異常は、様々な婦人科疾患や感染症のサインである可能性があります。
早期発見・早期治療のためには、それぞれの疾患の特徴を理解しておきましょう。
- 性器クラミジア感染症
- 膣カンジダ
- 膣トリコモナス症
- 子宮頸管炎
- 子宮頸管ポリープ
- 子宮頸がん
- 淋菌感染症
性器クラミジア感染症
性器クラミジア感染症は、クラミジア・トラコマチスという細菌による性感染症です。
日本で多い性感染症のひとつで、特に若い女性に多く見られます。
感染初期は無症状のことが多いのですが、進行すると黄色や白色の膿のようなおりものが増加し、不正出血を伴うことがあります。
また、排尿時の痛みや下腹部痛を感じる場合もあるでしょう。
治療せずに放置すると、子宮内膜炎や卵管炎を引き起こし、不妊の原因となるおそれがあります。
抗真菌薬による治療で改善しますが、再発しやすいため、生活習慣の見直しも大切です。
膣カンジダ
膣カンジダは、膣内に常在するカンジダ菌が異常増殖することで発症する感染症です。
健康な女性でも発症する可能性があり、決して珍しい病気ではありません。
症状として、白いカッテージチーズのような塊状のおりものが特徴的です。
同時に、膣や外陰部の強いかゆみ、灼熱感、腫れなどを伴います。
妊娠中、糖尿病、免疫力の低下、抗生物質の使用などが発症のリスクファクターとなります。
抗真菌薬による治療で改善しますが、再発しやすい傾向があるため、生活習慣の改善も重要です。
関連記事:カンジダ症の症状とは?原因・対処法・再発予防法について
膣トリコモナス症
膣トリコモナス症は、トリコモナス原虫による性感染症です。性的接触によって感染しますが、まれに公衆浴場やタオルを介して感染することもあります。
黄緑色で泡状のおりものが特徴的で、強い悪臭を伴います。
また、膣や外陰部の強いかゆみ、排尿時の痛み、不正出血などの症状が現れることがあります。
治療には抗原虫薬が使用され、パートナーも同時に治療を受ける必要があります。
治療中は飲酒を避け、医師の指示に従って薬を服用しましょう。
子宮頸管炎
子宮頸管炎は、子宮の入り口である子宮頸部に炎症が起こる疾患です。
クラミジアや淋菌などの感染症が原因となりやすいですが、非感染性の場合もあります。
膿のような黄色いおりものが増加し、不正出血や性交後の出血を伴うことがあります。
また、下腹部痛や腰痛を感じるケースもあります。
適切な治療を行わないと、感染が上行して子宮内膜炎や卵管炎を引き起こし、不妊の原因となる可能性があります。
原因菌に応じた抗生物質による治療が必要です。
子宮頸管ポリープ
子宮頸管ポリープは、子宮頸部にできる良性の腫瘍です。
ホルモンの影響や慢性的な炎症が原因で発症することが多く、特に更年期前後の女性に多く見られます。
血の混じった褐色のおりものや、性交後の出血が主な症状です。
ポリープが大きくなると、月経以外の出血量が増加することもあります。
多くの場合、外来での簡単な手術で切除できます。
良性の病変ですが、まれに悪性化することがあるため、定期的に検診を受けましょう。
関連ページ:子宮頸管ポリープの概要・手術について
子宮頸がん
子宮頸がんは、子宮の入り口である子宮頸部に発生するがんです。
HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が主な原因で、初期は無症状のことが多いのが特徴です。
進行すると、血の混じったおりものや不正出血、性交後の出血などの症状が現れます。
また、悪臭を伴うおりものが増加することもあります。
定期的な子宮頸がん検診を受けることで、前がん病変の段階での発見と治療が可能になります。
早期発見・早期治療により、良好な予後が期待できます。
【関連記事】子宮頸がんの精密検査にかかる費用と「LSIL」の検査内容
淋菌感染症
淋菌感染症は、淋菌による性感染症です。
性的接触によって感染し、男性では症状が現れやすいのに対し、女性では無症状のことが多いのが特徴です。
症状が現れる場合、黄色や緑色の膿のようなおりものが増加し、排尿時の痛みや不正出血を伴うことがあります。
また、下腹部痛や発熱を伴う場合もあります。
治療には抗生物質が使用されますが、近年は薬剤耐性菌の出現が問題となっています。
診察のご予約はこちら
おりもののケアを行うポイント
おりものの異常を予防し、健康な膣内環境を維持するためには、適したケアが重要です。
過度なケアは逆効果となることもあるため、正しい知識に基づいたケアを行いましょう。
- パンティライナーを使用する
- 下着やシートをこまめに取り替える
- 洗い過ぎに注意する
パンティライナーを使用する
パンティライナーは、おりものによる下着の汚れを防ぎ、清潔を保つのに役立ちます。
ただし、使用方法には注意が必要です。
パンティライナーは、通気性の良い素材を選びましょう。
合成繊維よりも天然素材を使用したものや、通気性を重視した製品を選ぶことで、ムレを防ぐことができます。
また、長時間同じパンティライナーを使用することは避け、3-4時間ごとに交換することをおすすめします。
特におりものの量が多い日や、暑い日などは、より頻繁に交換することが必要です。
かぶれやすい体質の方は、オーガニックコットンなどの天然素材を使用した製品を選ぶことが良いでしょう。
パンティライナーの使用によって、かえって感染症のリスクが高まることもあるため、正しい使用方法を守ることが大切です。
下着やシートをこまめに取り替える
下着とパンティライナーやナプキンの交換は、膣内の清潔環境を維持するために重要です。
おりものの量が多い日は、1日に2-3回下着を交換することが推奨されます。
特に夏場や運動後などは、汗とともに細菌が繁殖しやすくなるため、より頻繁な交換が必要です。
洗濯の際は、洗剤の残りを防ぐため、しっかりとすすぎ、よく乾かすことが大切です。
洗い過ぎに注意する
おりものは、膣内を清潔な状態に保つために必要な存在です。
おりものが気になるからと洗いすぎてしまうと、必要なおりものが洗い流されてしまい、膣内の環境悪化につながります。
おりものが必要な存在であることを理解し、過度な洗浄は避けるよう心掛けましょう。
おりものの変化で体調をチェックしよう
おりものは女性特有の生理現象であり、膣内の自浄作用を担う重要な存在です。また、健康状態を把握する手がかりにもなります。
おりものの正常な変化を理解し、日々の体調管理に役立てましょう。
「いつもと違う」「においが変わった」と感じた場合は、感染症の可能性もあるため、注意が必要です。
早めに医師へ相談し、適切な診察と治療を受けましょう。
渋谷・原宿・明治神宮前・表参道の婦人科・産婦人科 - LOG原宿
診察のご予約はこちら


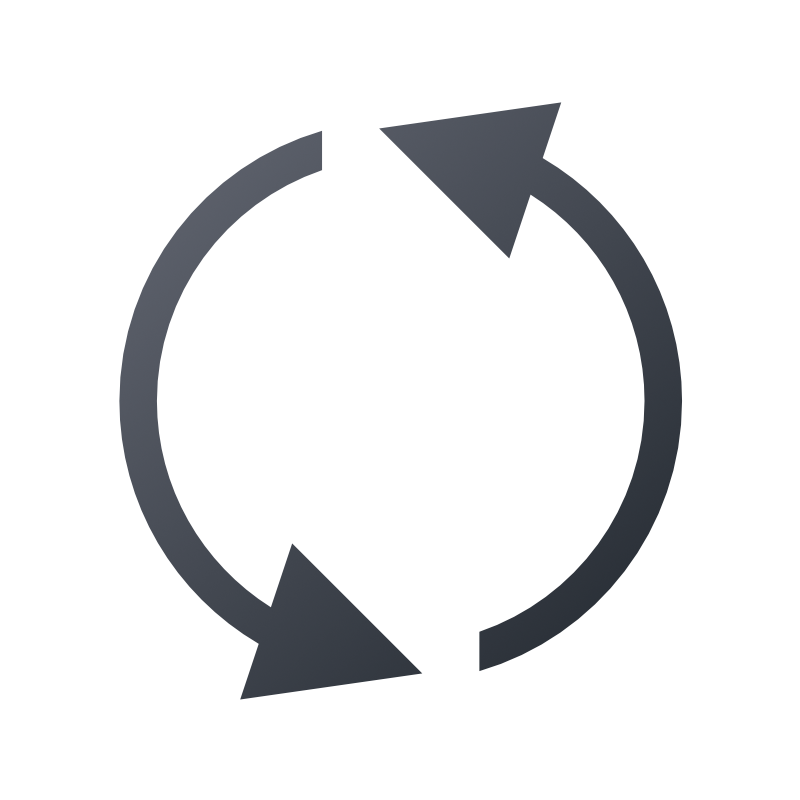 2025.11.04
2025.11.04