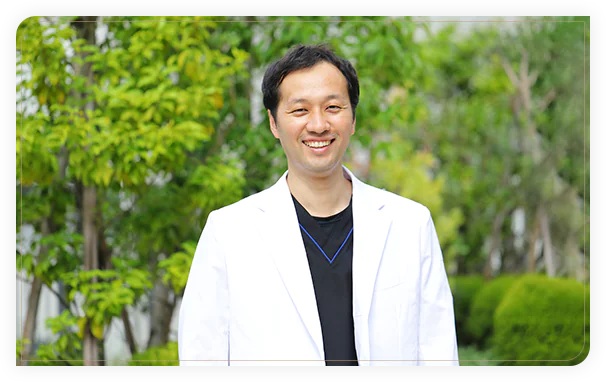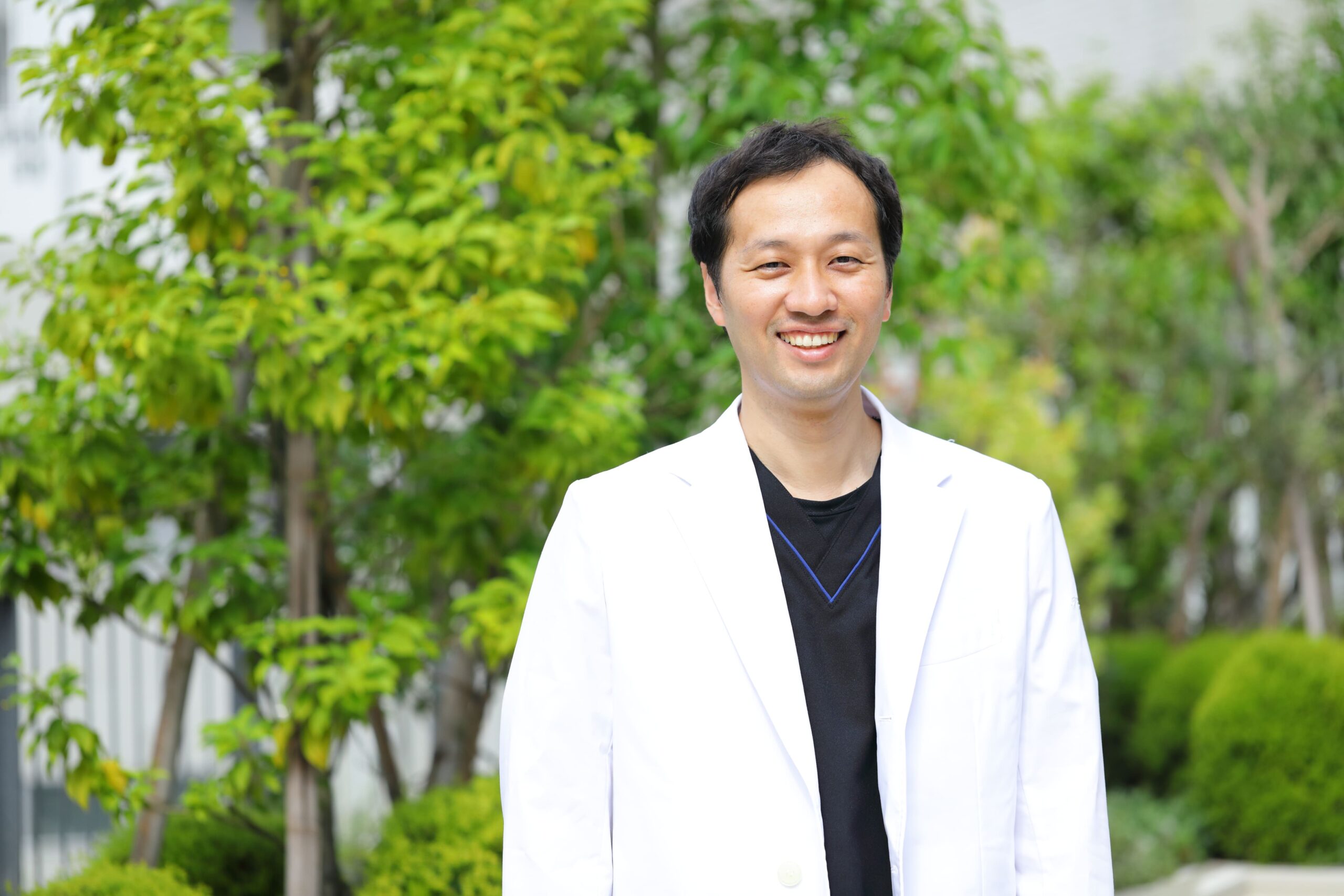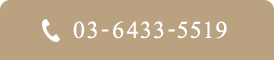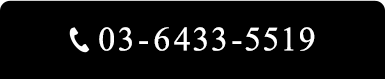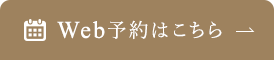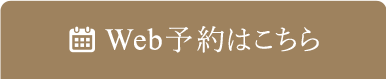病院で検査を受けて妊娠がわかったときは、出産までの期間定期的に健診を受ける必要があります。
妊婦さんが受ける健診は「妊婦健診」と呼ばれ、胎児の発育状況を確認し、母体の健康状態を把握するために重要な検査です。
しかし、仕事やプライベートが忙しい方の場合、正しい健診の頻度やタイミングがわかりづらく、スケジュールを合わせるのが難しいかもしれません。
この記事では、妊婦健診の目的や頻度、スケジュールや検査内容について紹介しています。妊婦健診について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
■関連ページ
妊婦健診とは?
妊婦健診は、妊娠中の母親の体と胎児の発育・健康状態を確認し、適切な対応をとるための医療検査です。
主な検査対象は母体で、血圧や体重測定、尿検査や血液検査のほか、胎児が正しく成長しているかを超音波検査で調べます。妊娠の経過に応じてさまざまなリスクが考えられることから、リスクの早期発見と早期対処を目的としています。
健診を通して母子の安全な妊娠・出産をサポートし、記録は母子手帳で管理します。
診察のご予約はこちら
妊婦健診の目的
妊婦健診の目的は、妊婦と胎児の健康を守ることです。
妊娠中は「妊娠高血圧症候群」「妊娠糖尿病」といった疾患のほか、貧血や感染症などにも注意しなければなりません。母子だけでは健康上のリスクに対処しきれないため、医師や看護師が連携してサポートを行います。
検査によって得られたデータを基に医師がリスクを説明し、妊娠中に起こりやすい異常や病気への理解を深めます。妊娠期間を適切に管理することで、重篤な疾患や合併症、早産のリスクを軽減できます。
さらに、胎児の成長や発育の様子を確認することで、発育不全や先天異常の兆候に気づくことができます。妊婦健診はお腹の赤ちゃんのためにできることを知り、妊娠・出産への理解を深めながら、不安や悩みを相談できる貴重な機会です。
【関連記事】妊娠中にLSIL・ASC-USと判断された場合のリスクと対応方法
妊婦健診はいつから受けるのか
妊婦健診は、妊娠が確認できた時点で早めに受診をスタートさせることが大切です。一般的に、妊娠が判明した段階で産婦人科を受診し、妊娠を確定させて妊婦健診のスケジュールを組みます。
初期の段階は4週間に1回の頻度が目安で、妊娠が進むにつれて健診の回数を増やします。妊娠後期に入ると、妊婦と胎児の健康状態を細かくチェックする必要があるため、2週間に1回のペースで健診し、出産の1ヶ月前には毎週健診を受けます。
必要に応じて薬が処方され、母体や胎児の健康維持を図ります。母体も急変や不調に備え、妊娠中に起こり得るリスクを可能なかぎり低減させる必要があるため、こまめな健診が重要です。
妊婦健診の頻度
厚生労働省は、標準的な妊婦健診の頻度を「妊婦健診Q&A」で紹介しています。
同省では標準的な健診回数として、次のように3期14回の健診を提示しています。
| 期間 | 健診の回数 | 健診の項目 |
|---|---|---|
| 妊娠初期〜23週 | 1〜4(4週間に1回) | 健康状態の把握 検査・計測 保健指導 各種検査 |
| 妊娠24週〜35週 | 5〜10(2週間に1回) | |
| 妊娠36週〜出産まで | 11〜14(1週間に1回) |
14回はあくまでも目安です。必要に応じて医学的検査を行う場合は、この限りではありません。
たとえば、血液検査や超音波検査、その他の検査は主治医の判断によって異なるため、主治医や医療機関と緊密に連携することが大切です。また、母体と胎児の健康状態や病院の方針によって通院回数が変わることもあります。
頻繁に病院へ通えない場合は、事前に妊婦健診のスケジュールや目安を把握したうえで、医療機関にご相談ください。
妊婦健診のスケジュールと内容
妊婦健診では、次のようなスケジュールで検査を行います。初回の受診でスケジュールを決めてから、健診は3期に分けて行われます。
初回受診から予定日決定
初回の受診は生理予定日の1〜2週間後が目安です。この時期に産婦人科を受診し、妊娠の状態を確定します。つわりなどの兆候がある方や、妊娠検査薬で陽性反応が出た場合は、その旨を説明します。
妊娠週数や最終月経日などを問診で確認し、尿検査・超音波検査・内診・血液検査などを行います。なかでも超音波検査は子宮内の胎嚢(たいのう)や胎児の確認を行うために重要な検査です。
血液検査は、子宮内に胎嚢が確認できなかったときにhCGの検査を行います。これは正常な妊娠か、あるいは子宮外への異常な妊娠(異所性妊娠)かを判断するために必要な検査になります。
これらの複数の検査結果を組み合わせて正常に妊娠しているかどうかを判断し、最終月経日などから妊娠週数を推定し、出産予定日を決めます。
妊娠が確定すると母子健康手帳が交付され、妊婦健診のスケジュールや日常生活を送るうえでの注意点について説明を受けます。初回の受診は妊娠を確定し出産予定日が決まるため、妊婦健診に入る前の重要な検査です。
注意点として、初回の健診は自費診療になる場合があります。問診や検査のために、基礎体温表やお薬手帳、生理用品を持参しなければならないケースもあるため、受診前に医療機関に持ち物を尋ねておくと安心です。
関連記事:バルトリン腺嚢胞はほっとくとどうなる?症状の特徴と検査方法を紹介
妊娠初期
妊娠初期(妊娠4週〜15週)は、4週間に1回の頻度で妊婦健診を受けます。
この時期は、成長中の胎児の心拍を確認し、胎芽の成長などをチェックします。超音波検査は期間内に2回程度が目安とされていますが、医療機関によっては健診のたびに超音波検査を行うこともあります。
母体の状態を診るために血圧測定・尿検査・体重測定・腹囲・子宮底長の測定・子宮頸がん検診・血液検査などが行われます。ここでの血液検査は母体の健康状態を把握するために重要な検査で、貧血や肝炎に罹患していないか、HIVや梅毒といった感染症の有無などを確認するものです。また、血液型や風疹やトキソプラズマ抗体検査が含まれます。いずれも子宮や母体に異常がないかを調べる重要な検査です。
検査結果に基づいて、「妊娠高血圧症候群」や「妊娠糖尿病」のリスク評価も行われます。妊娠中は普段と異なる症状が現れるケースも多いため、リスクを抑えるための生活指導や栄養指導が行われます。
妊娠中期
妊娠中期(妊娠16週〜27週)からは胎盤ができあがり、胎児が著しく成長する時期です。
初期と同じく、健診は4週間に1回のペースで行われます。超音波検査では胎児の大きさや心拍のほか、臓器の発達や性別が確認できるようになります。
母体の健康を確認するために血圧測定・尿検査・体重測定・腹囲・子宮底長の測定・血液検査・超音波検査が行われます。血液検査では期間内に1度、B群溶血性レンサ球菌検査を実施します。中期に入ると胎児が成長し胎動を実感できるようになります。
妊娠後期
妊娠後期(妊娠28週〜)は、胎児が出産に向けて大きく成長し、それに合わせて母体も急激に変化する時期です。
健診頻度は2週間に1回のペースとなり、妊娠36週を過ぎると毎週健診が行われます。内容は初期・中期と同様に、血圧測定・尿検査・体重測定・腹囲・子宮底長の測定・血液検査・超音波検査を行い、胎児の発育状態や心拍のほか、胎位の確認を実施します。
中期で、B群溶血性レンサ球菌検査を実施しなかった場合は、後期でこの検査を行います。また、内診での子宮口の状態を確認することや、NST(胎児心拍モニタリング)を行うこともあります。NSTは横になった状態でセンサーを取り付け、胎児の健康状態をチェックする検査です。
いよいよ出産に向けて準備をする時期となり、陣痛や破水、出血といった兆候への対処法や入院の準備などをスタートします。医療機関から出産や産後に関する説明を受けるのもこの時期で、こまめな健診で計画的に出産への準備を整えることが大切です。
診察のご予約はこちら
妊婦健診で一般的に行う検査内容
妊婦健診では、問診や体重測定、血圧測定など基本的な健康診断に加えて、腹囲や子宮底長など胎児の成長を確認するための検査が行われます。
ここからは、それぞれの検査内容について詳しくみていきましょう。
- 問診
- 体重測定
- 血圧測定
- 腹囲計測
- 子宮底長
- 超音波検査
- 尿検査
- 浮腫(むくみ)
- 保健指導
問診
問診は、妊婦の健康状態や妊娠・分娩歴の確認のほか、持病や手術歴などの既往歴、体調や生活状況などを総合的に確認する検査です。
初診時の問診ではつわりや妊娠検査薬の陽性反応があるか、腹痛や出血の症状があるかなどを確認し、睡眠や服用中の薬・サプリメントなど生活や食生活の状況も把握します。
総合的に聞き取りを行うことで、妊娠の経過中に考えられるリスクの予測がしやすくなり、早期対応をとりやすくなります。また、妊娠初期に入るにあたり不安なことや悩みがないかもヒアリングし、妊婦と医療機関との信頼関係を構築します。
医療機関は一人ひとりの妊婦と胎児の健康を支えるため、必要な支援や処置を見極めています。そのためには検査だけではなく問診も重要な要素といえるでしょう。
問診は健診ごとに実施され、体調の変化や困りごとがないか、異常や違和感がないかなどを確認します。問診の結果と各種検査の内容を組み合わせて、妊婦と胎児の健康状態をチェックします。
体重測定
妊娠中は母体と胎児が健康的に過ごせるように、正しい生活習慣を心がけなくてはなりません。
胎児が成長するにつれて母体への負担がかかることから、母体の体重を計測し、体重増加のペースが適切かを確認します。急激に体重が増えると「妊娠高血圧症候群」や「妊娠糖尿病」といった合併症のリスクが高まるため、食事や運動をアドバイスして予防を推奨します。
妊娠中の体重増加の目安は7〜12kgですが、母体や胎児の状態により個人差があるため、体重計測と医師の指導が必要になります。体重が急増した場合は生活習慣の見直しを提案し、急減したときは胎児の発育不全の可能性も踏まえて経過を観察しなければなりません。
妊娠中の体重は測定後にグラフ化し、血液検査や超音波検査といった他の検査結果とともに経過を観察します。
血圧測定
妊娠中はホルモンの変化などさまざまな理由で血圧が変動するため、血圧測定で健康状態を把握する必要があります。
血圧を測定する目的のひとつが「妊娠高血圧症候群(旧・妊娠中毒症)」のチェックです。妊娠によって毒素が体内に発生すると、むくみや高血圧の症状が現れます。この症状をそのままにしていると、母体のけいれんや胎児の発育不全を引き起こすことがあります。
妊娠高血圧症候群は母子ともに健康上のリスクが高い症状のため、血圧を測定して異常を早期に発見する必要があるのです。
妊娠中の血圧の基準は140/90mmHg未満とされています。万が一この数値を超えたときは、精密検査や管理入院が必要になることもあります。
腹囲計測
妊娠中、胎児の成長度合いや羊水量の変化を確認するために腹囲を計測します。胎児の推定体重、羊水量の過多や過少状態を推定できるほか、子宮の大きさを大まかに把握する際にも活用されている検査です。
腹囲が急激に増加した場合は、羊水過多や双胎妊娠、または妊娠糖尿病といった症状に罹患している可能性が考えられます。一方、腹囲の増加が乏しい場合は、胎児の発育不全や羊水過少がリスクとして考えられます。
妊娠初期からどの程度腹囲が増加したかは個人差が大きく、超音波検査やその他の検査の結果とも照らし合わせながら総合的に状態を判断します。
子宮底長
子宮底長とは、恥骨の上端から子宮の底部までの長さを測る検査です。
妊娠すると腹囲の増加とともに子宮底長も長く伸びるため、妊娠20週ごろから胎児の成長や羊水量が推定できるようになります。腹囲と同様に外側からメジャーを使って測るため、痛みなどはありません。
子宮底長の長さが標準値より大きい場合は多胎妊娠・羊水過多のリスクが考えられ、標準値より小さい場合は胎児の発育不全を考慮します。
ただし、測定方法のばらつきや腹囲や子宮底長の大きさ・長さに個人差があることも踏まえる必要があり、子宮底長の長さだけをみて判断することはありません。
超音波検査
超音波検査は、胎児の成長や姿を確認できる画像診断の一種です。
超音波検査によって妊娠初期から胎児の心拍が確認でき、中期に入ると胎児の頭やお腹などが測定できます。成長の程度を数字で評価し、さらに羊水量や胎盤の位置といった母体の状況も含めて、目視での確認がとれるようになります。
超音波検査は経腟または経腹で行われるため、検査中の痛みはありません。
尿検査
尿検査は、尿中に含まれるたんぱく・糖・潜血を調べ、健康上のリスクや異常の早期発見に役立てられています。
尿たんぱくが検出された場合「妊娠高血圧症候群」の兆候の可能性が疑われ、早期発見・早期対処に役立てることができます。尿糖は「妊娠糖尿病」の指標として用いられ、尿糖が検出されたときは血糖検査を並行して評価します。
尿中に含まれる細菌や白血球から、尿路感染症が見つかることもあります。健康上のリスクや疾患の兆候を早期に発見するために重要な検査です。
浮腫
浮腫(むくみ)は、妊娠中に起こりやすい症状のひとつです。
下肢に多く見られ、生理的なむくみと妊娠高血圧症候群の初期症状が似ていることから、慎重に区別しなければなりません。
視診や触診で浮腫の有無や程度を確認し、急激な体重増加がみられないか、血圧測定や血液検査の結果も併せて確認します。
保健指導
保健指導は、妊娠中の健康維持や胎児の成長をサポートするために行われる指導や相談です。
お母さんと赤ちゃんの状況は一人ひとり異なります。健診の結果がいつも同じとは限らないため、健診ごとの結果やライフスタイルに関する問診も踏まえながら、栄養バランスの取れた食生活や睡眠、ストレスへの対処方法をアドバイスします。
妊娠中期以降は、出産に向けた心構えや育児の準備、支援制度の情報提供を行います。
診察のご予約はこちら
妊婦健診の費用
妊娠は病気やケガではないため、妊婦健診にかかる費用は基本的に自費診療となります。
1回あたりの費用は基本的な検査のみであれば3,000~7,000円程度、その他の検査を含むと1万円を超えることもあります。
ただし、自治体ごとに助成制度や公費負担制度を設けているため、健診にかかる費用の一部が助成され、負担を軽くすることができます。
妊婦健診を受けないとどうなる?
妊婦健診は約14回にわたって行われますが、健診を受けないことでどのようなリスクが考えられるのでしょうか。
- 合併症のリスクが高まる
- 周産期死亡率が上がる
- 病院で受け入れ拒否される可能性がある
合併症のリスクが高まる
妊婦健診は、妊娠中に発症しやすい症状や異常を早期に発見し、治療やサポートを行うための検査です。健診を受けなければ異常が進行した状態でも気づきにくく、重篤な症状や合併症を引き起こすリスクが大幅に高くなります。
周産期死亡率が上がる
周産期とは、妊娠満22週〜生後1週未満までの期間です。この間に起こる胎児や新生児の死亡を「周産期死亡」と呼びます。
妊婦健診を受けないと、周産期死亡率が高くなる可能性があります。胎児が子宮内で発育不全に陥っても気づかず、胎児死亡に至るようなケースです。
分娩中の異常(遷延分娩・臍帯巻絡・胎盤早期剥離など)も、事前に検査や準備を行うことで適切に対応できますが、情報がなければ対処が追いつかず、新生児死亡につながるリスクがあります。
病院で受け入れ拒否される可能性がある
妊婦健診を受けていない、長期間受診していない妊婦が出産のために病院を訪れる場合、病院側がリスクを十分に管理できないために、分娩を保証できないとして受け入れを拒否するケースがあります。
分娩は母体と胎児双方の健康に留意しながら行わなければなりません。緊急帝王切開のように予測できない事態も起こり得るために、医療機関では事前の健診受診や妊婦登録を出産受け入れの条件としているのです。
診察のご予約はこちら
妊婦健診は適切なタイミングで受診することが大切
今回は、妊婦健診の内容やスケジュール、健診にかかる費用について紹介しました。
妊婦健診は、妊娠期のお母さんと赤ちゃんに起こり得るさまざまなリスクを防ぐために重要な検査です。妊娠中は、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のような代表的な疾患に加えて、貧血や感染症にも注意しなければなりません。
病院や助産院の受診頻度は通常よりも多くなりますが、母子の安全を守ることにも繋がるため、適切なタイミングで受診を検討しましょう。
渋谷・原宿・明治神宮前・表参道の婦人科・産婦人科 - LOG原宿
診察のご予約はこちら


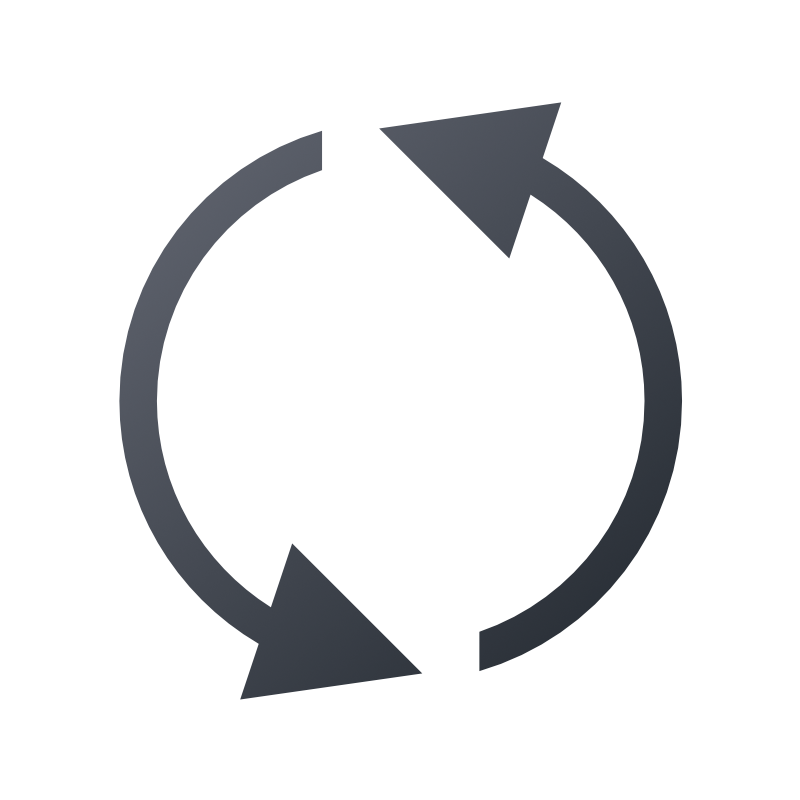 2025.11.04
2025.11.04