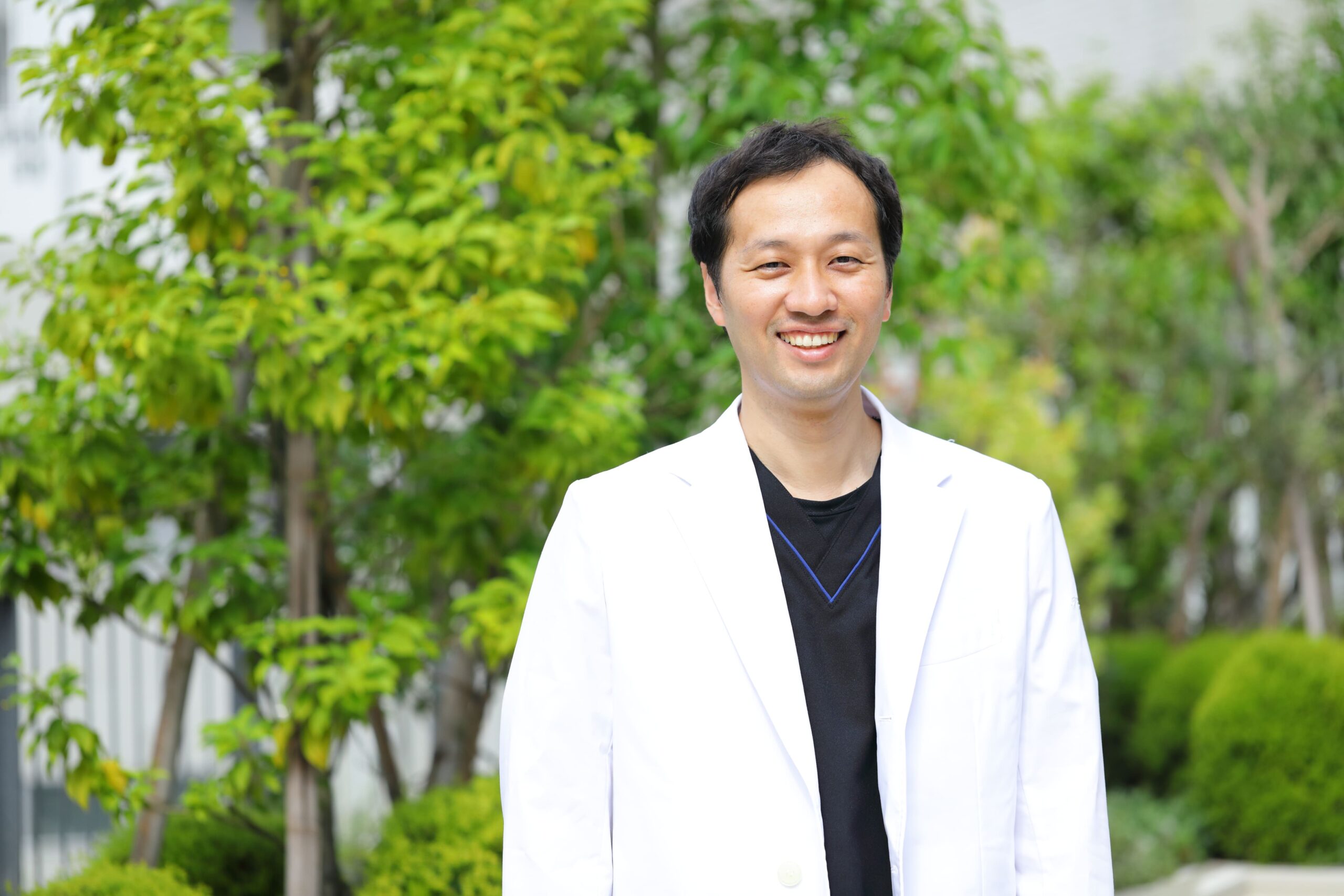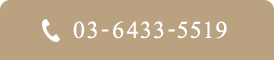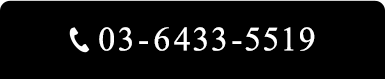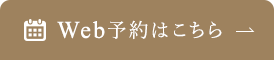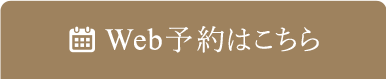子宮頸がん検診は、おなかに赤ちゃんがいるとわかったら必ず受けなければなりません。
ASC-HやHSILなどの異常が疑われる結果だった場合は「どうしたらいいんだろう……」「赤ちゃんへの影響は?」と不安が募りますよね。
そこで今回は、妊娠中に子宮頸がん検診に引っかかる可能性の有無や、対処法を解説します。
妊娠中の不安を軽減し、健康的で充実した毎日を送るために、ぜひお役立てください。
妊娠中に受ける子宮頸がん検診で異常は発見されるの?
結論から申し上げますと、妊娠中でも子宮頸がん検診で異常が発見されることはありえます。
実際に、検診を受けた妊婦1,500人のうち、子宮頸部の細胞に異常がみられた方は1.63%いたという研究結果も出ています。
なかには「異常ってがんのこと?」と、不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
検診で見つかった異常は、必ずしもがんであるとは言い切れません。
というのも、がんの一歩手前の状態にあたる“子宮頸部異形成”の可能性もあるためです。
子宮頸部異形成は、子宮の入り口に正常ではない細胞が発生している状態を指します。
状態が悪化するごとに子宮頸がんへと進展するリスクが高まる病変で、自覚症状はありません。
子宮頸部に起こる異常の原因
子宮頸部異形成、および子宮頸がんが起こる原因は、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染です。
HPVの感染経路は性交渉で、妊娠している、していないにかかわらず感染するおそれがあります。
今までは異常がみられなくとも、妊婦になってから「子宮頸部に異常が見つかった」という状況に陥ることも少なくありません。
赤ちゃんを授かったということは、性交渉を経ているわけですから、妊娠しているとHPVに感染している可能性があると考えられます。
おなかに赤ちゃんがいるとわかったタイミングで子宮頸がん検診を受ける理由
妊娠発覚後に子宮頸がん検診が必須となっているのは、先ほどお伝えしたようにHPVに感染している可能性があるからというだけではありません。
それにくわえて、子宮頸部に異常が生じうる時期と多くの方が妊娠するタイミングがリンクしていることも挙げられます。
罹患のリスクが高まる、また妊娠する可能性があるのは、20~30代と考えられます。
近年では、子どもを望まない夫婦や高齢での出産も増加しているため一概には言えませんが、目安としてはこの時期です。
日本国内では20歳から子宮頸がん検診を受けられるものの、受診率はおよそ35%と、それほど高くありません。
こうした状況下においては、妊娠するまで一度も検診を受けたことがない女性もいると考えられますから、赤ちゃんを授かったタイミングでの受診が必須とされているのです。
さらに、おなかが大きくなるにつれて、子宮の柔らかさや大きさも変化していきます。
週数が進むほど正確に診断できなくなることも踏まえると、検診を受けるのは妊娠初期がベストなタイミングとなります。
診察のご予約はこちら
妊娠中の子宮頸がん検診の結果でみられる用語
子宮頸部になんらかの異常が生じていた場合は、子宮頸がん検診の結果に以下の用語が記載されます。
子宮頸がん検診の結果でみられる用語
- ASC-US
- LSIL
- ASC-H
- HSIL
これまで検診を受けたことがないと、見慣れない用語ばかりでどのような意味があるのかがわからない方もいらっしゃるかもしれません。
以下で、一つずつ確認していきましょう。
ASC-US
ASC-US(アスカス)は、子宮頸部の細胞に軽度の病変が疑われる状態です。
子宮頸がん検診を受けた方に多くみられる結果で、その割合としては20~30人に1人程度とされています。
軽度の病変と聞くと不安に思われるかもしれませんが、ASC-USと判定されても子宮頸がんに罹患しているわけではありません。
子宮頸部の細胞に起きている変化が小さいため、正常ではないものの異常とも言いがたい、いわゆる“グレーゾーン”の状態を示しています。
注意すべき異常はみられませんが、人によってはASC-USよりも状態が悪くなる可能性が無きにしもあらずということです。
そのためASC-USという結果が出た場合は、検査を受けた医療機関を受診するのがベターです。
関連記事:ASC-USとは?ASC-USの原因や子宮頸がんとの関連について
LSIL
HPVに感染し、軽度の異常が認められる状態をLSIL(ローシル)といいます。
軽度異形成(CIN1)ともよばれる状態で、ASC-USと同様、身体には特に影響はありません。
治療せずとも治りうるもののため、経過観察となることがほとんどです。
とはいえ、自然治癒せずに次の段階へと進んでしまうことも少なくありません。
子宮頸がん検診でLSILという結果が出たら、精密検査を受ける必要があります。
また、妊娠中は精神的にゆらぎやすい時期ですから、小さな出来事でもストレスを感じてしまいがちです。
異常がみられたとしても「治る可能性もあるから大丈夫」と、心配しすぎずに毎日を送るのも大切です。
関連記事:LSILとは?LSILと言われたら?精密検査をする理由と癌の確率
ASC-H
中等度、もしくは高度の子宮頸部異形成が疑われる場合、ASC-H(アスクエイチ)と判定されます。
この結果が出たときは、より詳細に身体の状況を把握し、適切な治療を受ける意味でも必ず精密検査を受けましょう。
子宮頸部の表面にある細胞が悪性化している可能性があるため、放置しておくと子宮頸がんへと進展するかもしれません。
関連記事:ASC-H(アスクハイ)とは?検査と治療の方法を解説
HSIL
HSIL(ハイシル)は、子宮頸部の表面にある細胞に高度の異常が起きている状態を指します。
かみ砕いて言うと、子宮頸がんの一歩手前のような状態です。
この段階まで進むと、精密検査の結果次第では、手術を受けなければならない可能性もあります。
なお、HSILと判定される方はあまり多くないため、過度に恐れなくてよいでしょう。
関連記事:HSIL(ハイシル)とは?結果後の検査や治療の方針について解説
妊娠中にASC-HやHSILと判定されたときの対応
子宮頸がん検診での判定には、さまざまな種類があるとおわかりいただけたのではないでしょうか。
なかでも、子宮頸がんに罹患するリスクが高まるASC-HやHSILという結果が出たときは「どうしよう……」と心配になるものです。
そこで本項では、妊娠中にこうした判定がなされたときの対応をお伝えします。
経過観察で様子を見る
子宮頸がん検診でASC-HやHSILという結果が出ても、すぐに手術を受けなければならないわけではありません。
緊急性が低い場合は手術ではなく、経過観察となります。
経過観察では、3~4か月ごとに細胞診や精密検査を受けて、HPVへの感染の有無や異常の変化を確認します。
特に異常が見つからなければ通常検診に戻りますが、感染が続いていたり状態が悪化していたりするときは、手術が施されるのが一般的です。
手術を受ける
ASC-HやHSILと判定されたのちに受けた精密検査の結果、高度の子宮頸部異形成やがんが認められたときは、手術が必要となります。
おなかの中の赤ちゃんと母体の命を守るため、妊娠中に手術を受けることになった場合は、妊娠週数に気をつけなければなりません。
妊娠14~15週前後、つまり妊娠初期の最後の月までに手術を受けるのがベターです。
ASC-HやHSILと判定されたとき、妊娠中でも受けられる手術は、3つあります。
円錐切除術
まず挙げられるのが、円錐切除術です。
この手術では、正常ではない細胞の一部を、電気メスやレーザーで円錐状に切り取ります。
異変が起きている箇所を丸ごと切り取れるため、手術がきちんと施されていれば再発の可能性は低いでしょう。
切り取った部分は病理検査や組織検査が行われ、子宮頸部異形成、また子宮頸がんを発症しているかどうかの診断が確定されます。
妊娠中に円錐切除術を受ける場合は「子宮付近に傷をつけても大丈夫なのかな?」と思われるかもしれません。
しかし、病変を切り取る範囲は最小限ですので、ご安心ください。
子宮の入り口にあたる子宮頸部は、出産が始まるまで閉じている必要がありますから、慎重に手術が施されます。
レーザー蒸散術
HPVへの感染が長く続いている場合には、レーザー蒸散術が施されることがあります。
異形成をレーザーの光で焼灼する手術で、子宮に与える影響が少ないうえに、出血や痛みも抑えられるのが特徴です。
子宮頸部異形成がそれほど進行していない方や、痛みに弱い方の役に立つでしょう。
しかし、病変が起きている部分を切り取るわけではないため、確定診断を得られません。
ですから、ご自身の身体の状態をきちんと把握したいと思われる方は、医師と相談のうえほかの手術をご検討ください。
子宮摘出術
子宮頸がんが進行し、深さが3mm以下になる、IA1期という時期を超えたときは、場合により子宮を摘出しなければなりません。
このまま放置しておくと子宮頸部にとどまらず、リンパ節や直腸の粘膜までがんが広がるおそれがあるためです。
妊娠中に子宮頸がんに罹患したとしても、がんの進行は比較的緩やかであるため、病状が急激に悪化するとは考えにくいものです。
しかし場合によっては、命を落とす危険性がある状態になり、妊娠を諦めざるを得なくなるかもしれません。
ご自身の身体を守り、そして授かった大切な宝物と素敵な毎日を送るためにも、異常が見つかったときにすぐ手を打つことが大切です。
妊娠中に実施される子宮頸がん検診の内容
おなかの中の赤ちゃんを守るためにも、妊娠初期に子宮頸がん検診を受診するのが大切だとわかりました。
ここでは、妊娠中にどのような検査が実施されるのかを深掘りします。
妊婦の方が受ける子宮頸がん検診は、“細胞診のみ”となることがほとんどです。
この結果で異常がみられた場合は、精密検査として“ハイリスクHPV検査”や“コルポスコピー検査”が実施されます。
細胞診
細胞診は、子宮頸部の表面にある細胞が正常な状態かどうかを調べる検査です。
子宮の入り口付近をブラシで優しくこすって細胞を採取したのち、顕微鏡で調べます。
妊婦の方は必ず受けることとなる検査で、子宮頸がんに進展する可能性を判別するのが目的です。
子宮の入り口付近に刺激を加えるため「痛みが出そう……」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
個人差はあるものの、違和感を覚える程度で痛みは感じにくいといわれていますので、ご安心ください。
特に異常がなければ、この段階で子宮頸がん検診は終了です。
ハイリスクHPV検査
細胞診の結果、ASC-USと判定された場合には、ハイリスクHPV検査を受けます。
ハイリスクHPV検査は、子宮頸部異形成や子宮頸がんの原因となるHPVに感染しているかどうかを調べる検査です。
実はHPVの種類はさまざまで、その数は200を超えるといわれています。
しかし、200種類すべてのウイルスが異常を引き起こすわけではありません。
異常が起こるのは、このうち“ハイリスク型”とよばれる、約13種類のいずれかに感染した場合です。
ハイリスクHPV検査では、感染しているウイルスの型まではわからないものの、陽性・陰性を判断できるため、子宮頸部の異常の発見につながります。
細胞診と併用することで、異常を見逃すリスク軽減できるはずです。
コルポスコピー検査
細胞診で異常が疑われた、かつハイリスクHPV検査で陽性と判定されたら、病変の進行状況を調べるために、コルポスコピー検査を受けることとなります。
コルポスコピー検査は、“コルポスコープ”といわれる拡大鏡を用いて、肉眼では見えない子宮頸部の表面を観察する組織検査です。
観察と同時に、異常が生じている組織も採取されます。
まず、膣を開く器具をつけて子宮頸部に酢酸を塗り、色の変化を確認します。
病変があると変色するため、進行状況を確認できるわけです。
コルポスコープで子宮頸部の表面の様子を確認できたら、変色がみられた部分の組織を採取し、検査自体は終了となります。
コルポスコピー検査も、細胞診と同様に痛みは出にくいのでご安心ください。
しかし人によっては、膣を開く器具をつけたり異常がある箇所の組織を採取したりする際に、チクッとした痛みを感じるかもしれません。
いずれも軽度ですが、強い痛みが続く場合は、内服薬や坐薬などを使用して痛みを軽減させることもできます。
妊娠中に子宮頸がんが起きた場合、赤ちゃんに転移する可能性はあるのか
妊娠中に子宮頸がんを発症したとしても、赤ちゃんに影響が及ぶとは限りません。
繰り返しにはなりますが、子宮頸がんはHPVへの感染が引き金となるためです。
ですから、なんらかの問題が生じていても過度に不安を抱える必要はありません。
しかし円錐切除術を受けた場合は、低出生体重児や新生児死亡のリスクが上がるとも考えられているため、可能性はゼロではないと覚えておきたいところです。
また、2021年に発表された国立がん研究センターの研究では、子宮頸がんに罹患した母親から生まれた子どもに小児がんが見つかったという結果も出ています。
こうしたリスクを減らすためにも、迅速かつ適切な対応をとることが大切です。
参照元:国立がん研究センター『母親の子宮頸がんが子どもに移行する現象を発見』
妊娠中にASC-HやHSIL と判定されたら、すぐに医療機関を受診しよう
今回は、妊娠中にASC-HやHSILと判定されたときの対応をお伝えしました。
妊娠初期に受ける子宮頸がん検診の結果、ASC-HやHSILと判定されたら、すぐに精密検査を受けましょう。
気づかぬうちに状態が悪くなり、最悪の場合、妊娠を諦めなければならなくなるかもしれません。
精密検査の結果、軽度の異常であれば経過観察となりますが、手術が必要となる可能性もあります。
妊娠中の子宮頸がん検診で、ASC-HやHSILと判定された方は、Ladies clinic LOG 原宿にご相談ください。
精密検査にくわえて、子宮頸部異形成や子宮頸がんに有効な手術も提供しております。
原宿駅・渋谷駅徒歩7分の婦人科・産婦人科 LOG原宿について
診察のご予約はこちら

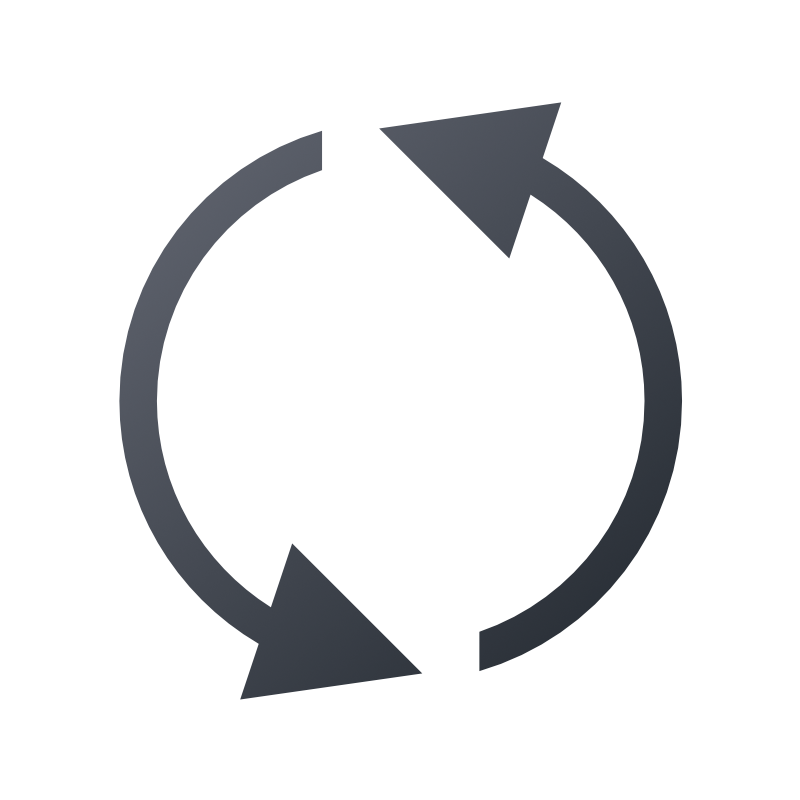 2025.07.06
2025.07.06