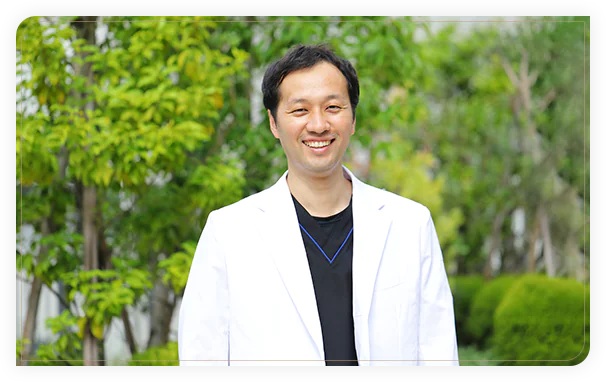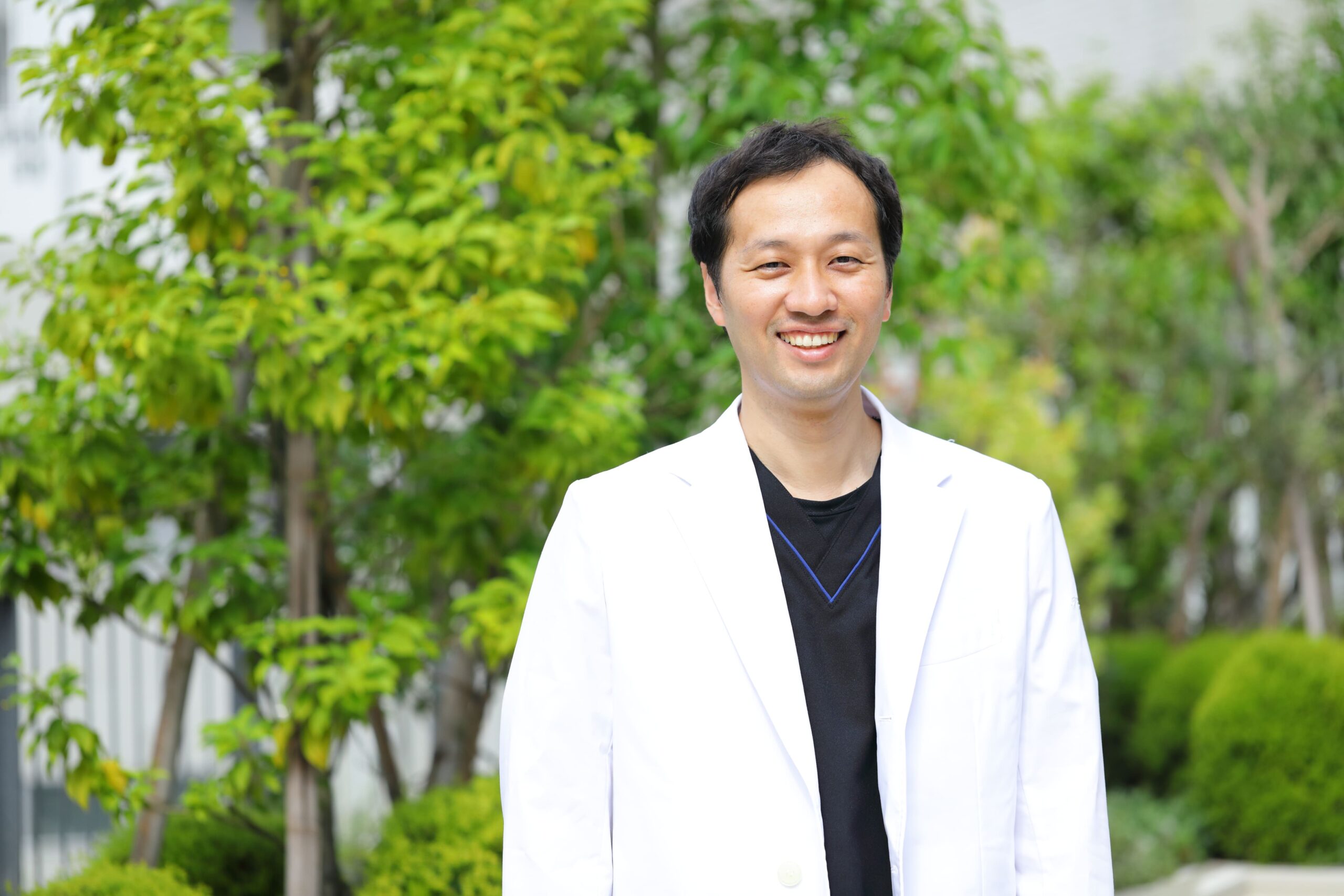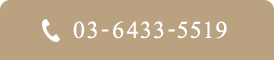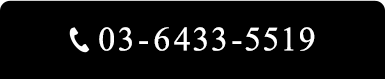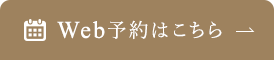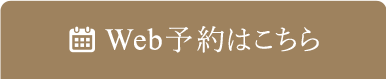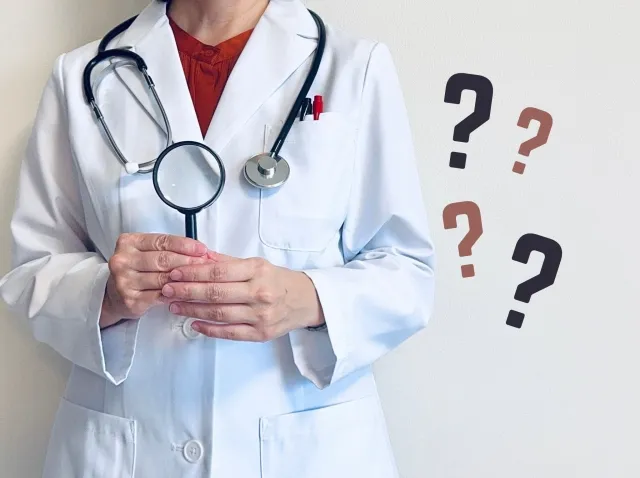
バルトリン腺とは、女性の外陰部にある小さな分泌腺の名称です。膣口の左右に一対で存在し、1〜2cm程度の管状の組織です。
バルトリン腺の役割は潤滑液を分泌し、膣の内部を滑らかにして、粘膜の損傷や感染症のリスクを低減することです。しかし、何らかの原因で腺の出口が詰まってしまうと、分泌液が内部に溜まってしまいます。
この記事では、バルトリン腺が腫れる「バルトリン腺嚢胞」について、特徴や再発率、再発の原因と症状を詳しく紹介します。どのような仕組みで発生し、再発するのか取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
■関連ページ
バルトリン腺嚢胞の再発率はどのくらい?
バルトリン腺嚢胞とは、膣の入口付近にあるバルトリン腺の出口が詰まり、内部に液体が溜まって膨らんだ状態を指します。
バルトリン腺嚢胞にはどのような特徴があるのか、再発率と併せてみていきましょう。
バルトリン腺嚢胞の特徴
バルトリン腺嚢胞は、管の内部に腺液が溜まって膨らみ、嚢胞として形作られる良性の疾患です。20代後半〜40代の女性に多いとされています。
良性疾患のため、患部を清潔にして経過観察をすることで自然治癒が期待できますが、嚢胞が細菌感染を起こすと「バルトリン腺膿瘍(のうよう)」と呼ばれる状態に進行します。
嚢胞自体も膨らみを伴うもので、摩擦によって違和感を覚えることがあります。さらに進行したバルトリン腺膿瘍は強い痛みや熱感、歩行が難しくなるといった自覚症状をきたしやすいことが特徴です。
嚢胞や膿瘍を放置していると歩行に支障をきたすおそれがあるため、必要に応じて患部の切開・排膿、開口部をつくって再発を防ぐ開窓術(かいそうじゅつ)を行う場合もあります。
【関連記事】バルトリン腺嚢胞はほっとくとどうなる?症状の特徴と検査方法を紹介
バルトリン腺嚢胞の再発率
バルトリン腺嚢胞は、治癒または治療後にも再発する可能性が比較的高い症状です。感染を伴うバルトリン腺膿瘍に進行したり、排膿のみ処置を行ったりした場合は再発率が20〜30%程度になるともいわれています。
嚢胞の治療には開窓術(造袋術)のほか、嚢胞とバルトリン腺をすべて摘出する摘出手術が選ばれます。再発を防ぐためには摘出手術が効果的ですが、排膿処置や嚢胞を切開して開口部をつくり、閉塞しにくくする開窓術が一般的です。
バルトリン腺嚢胞が再発する原因
バルトリン腺嚢胞が再発する原因は、細菌感染や分泌物の蓄積などが挙げられます。
分泌物が粘稠化し蓄積
バルトリン腺の分泌物が粘り気を帯びて「粘稠化(ねんちゅうか)」すると、膿がその場に留まり排出されにくくなります。
その結果、バルトリン腺の出口が詰まり、分泌物が腺内に溜まっていくことで嚢胞が形成されて再発しやすくなるのです。
細菌感染と炎症
細菌が導管に侵入すると免疫反応により炎症を引き起こし、導管の狭窄や閉塞が起こります。分泌物が外に出ていきにくくなると、嚢胞が再発しやすくなります。
ホルモンバランスの変化
排卵期や妊娠中は、女性ホルモンのバランスが変化するためバルトリン腺の分泌が活発になります。分泌物が過剰となり、導管内に蓄積すると再発リスクが高まります。
その他の原因
導管の開通が不十分、または摩擦や通気性の悪い下着などによる外的刺激、免疫低下はいずれも再発リスクを高める要因です。
バルトリン腺嚢胞が再発した際の主な症状
次に、バルトリン腺嚢胞が再発した際の主な症状をみていきましょう。
無症状の場合
バルトリン腺嚢胞は、再発してからすぐに痛みや不快感を伴うものではありません。なかには無症状のまま再発し、放置することで悪化するケースがみられます。
嚢胞が小さいうちは発赤や圧痛がなく、生活にも特に支障が出ないため、問題ないものとして放置されてしまいます。しかし皮膚の内部では分泌物が溜まり、放置していくと徐々に嚢胞が大きくなります。
関連記事:おりものとは?異常がある時の色やにおいの原因を解説
腫れや痛み
無症状以外では、腫れや痛みを伴うことがあります。嚢胞がある程度の大きさに成長し、組織を圧迫すると違和感や鈍い痛みが発現します。しこりのように指で触れられる大きさになると圧痛をきたすケースが一般的です。
性交時の痛み
再発したバルトリン腺嚢胞は、性交時にも痛みを引き起こすことがあります。嚢胞が膣の至近距離に位置しているため、性交中に触れてしまい、痛みを感じて支障をきたすケースです。
性行為の妨げになるだけではなく、性交後にも痛みが残存することも少なくありません。「痛いから」と、パートナーとのスキンシップや性行為の回避行動に繋がることもあります。
歩行困難
バルトリン腺嚢胞がしこりとして大きくなってくると、腫れから会陰部の圧迫感や歩行時の痛みが発現します。歩くときだけではなく椅子に座ったり立ち上がったりするときも嚢胞が摩擦で擦れ、そのたびに痛みや違和感を覚えることがあります。
炎症が強いときは痛みや熱感が嚢胞の周辺に広がり、安静にしていても違和感や痛みを覚えやすくなります。歩行困難など日常生活への影響を避けるため、早めの治療を検討しましょう。
細菌感染
バルトリン腺嚢胞が再発し、導管に細菌が侵入すると「バルトリン腺膿瘍」に進行することがあります。
細菌感染による免疫反応で、嚢胞内には膿が溜まり、腫れ・強い痛み・熱感・発赤といった炎症症状が現れます。症状が重くなると発熱や悪寒のような全身症状に発展することもあります。
細菌感染に対しては、患部を清潔に保ち排膿を行い、抗生物質の内服や外用薬の使用が一般的です。
バルトリン腺嚢胞が再発した際に受ける検査
バルトリン腺嚢胞が再発した際に受ける検査を詳しくみていきましょう。
問診
バルトリン腺嚢胞が再発したときは、問診で具体的な症状を調べます。過去の治療履歴や現在の状態を総合的に確認し、腫れや痛みの発症時期や再発の回数・頻度なども尋ねられます。
手術歴や性感染症の既往歴がある場合は、具体的な履歴をチェックします。問診の段階で詳細に履歴を尋ねることで、感染の可能性や再発のリスクか、必要な処置や検査対応の判断が可能です。
臨床診断
問診の後は臨床診断として、視診や触診を中心に患部の状態を診察します。外陰部にできた嚢胞の腫れの大きさや硬さ、熱感や赤み、痛みや膿の有無をチェックします。
嚢胞の位置・形状のほか、悪性かどうかの判断も臨床診断の段階で行います。診察の結果を踏まえ、さらに精密な診断が必要な場合は精密診断を実施します。
精密診断
精密診断は、再発を繰り返す、または通常と異なる状態の嚢胞がみられるときに行われる検査です。代表的な方法に超音波検査が挙げられ、嚢胞の内部や内容物の性状などを確認し、検査へと進みます。
細菌培養検査・病理検査
感染を伴う嚢胞は、分泌物や膿の採取とともに細菌培養検査を実施します。この検査によって、感染源である細菌の特定、適切な抗生物質の選定が可能です。
異常が疑われる嚢胞には、組織の病理検査が行われます。病理検査では組織の細胞構造を顕微鏡で調べ、異形成や癌の有無を診断します。
診察のご予約はこちら
バルトリン腺嚢胞が繰り返し再発する場合の治療方法
バルトリン腺嚢胞は完治しても再発することがあります。ここでは、再発を繰り返している場合の治療方法を確認しましょう。
保存的な治療
バルトリン腺嚢胞が大きくなく、痛みや感染もみられなければ、保存療法として医療処置を行わずに自然治癒を待つことがあります。
すぐに治療が必要な段階ではないため、嚢胞が自然に縮小し消失するのを待ちます。ただし患部は清潔にして、刺激を可能なかぎり与えないように注意します。医師の判断で抗生物質が処方されることもあり、膿瘍へ進まないように予防措置がとられます。
自宅でできるケアとして、血行を促して自然治癒を促す「座浴」が推奨されることもありますが、感染のおそれがある場合は座浴だけで症状を完治させることはできません。
保存療法は身体への負担が少なく、切開による痛みもありません。ただし、痛みや腫れが強まった場合には、より積極的な治療に切り替える必要があります。痛みや腫れが強くなった場合には、より積極的な治療法への切り替えが検討されます。
切開術
切開術は、感染を伴って腫れや痛みが強いバルトリン腺膿瘍に対して行われます。症状が急激に悪化した場合の第一段階の治療法として用いられる治療です。
膿瘍ができている部分を局所麻酔によって小さく切開し、膿を外に排出します。激しい痛みは排膿によって緩和されますが、根本的な対処法ではないため、再発防止策として開窓術や造袋術が必要になることもあります。
開窓術
開窓術は造袋術とも呼ばれ、再発する嚢胞や、排膿だけでは効果が不十分な場合に行われる治療法です。
嚢胞や膿瘍を局所麻酔下で小さく切開し、切開部の皮膚と嚢胞壁を縫合して開口部を形成します。これにより、内部の分泌物や膿がスムーズに外へ排出され、再閉塞を予防できます。
局所麻酔と小さな切開のみで完結する処置のため、低侵襲かつ日帰りが可能な処置です。術後は数日〜1週間程度安静にしながら治癒を待ち、その後は通常通り日常生活を送ることができます。
開窓術は一度実施すればバルトリン腺嚢胞の再発率を低減させられます。患部が再発を繰り返す場合に、優先的に適用できる治療法です。
嚢胞摘出術
嚢胞摘出術は、バルトリン腺嚢胞や膿瘍が再発し、他の治療法では効果が薄いときに行われる外科的治療です。
手術によって嚢胞や腺組織を摘出するため、再発のリスクを大きく低減させられます。手術は局所麻酔または全身麻酔下で行われ、術後は疼痛や傷跡が残る可能性があります。
術後は患部を安静にして過ごす必要があり、数日間の静養と通院が必要となることがあります。手術の可否は患者の年齢や健康状態、再発の回数を考慮しなければなりません。
患者の状態や医師の判断によって、再発のおそれが少ない・手術の必要がない・開窓術で対応できるといった場合は、身体的な負担が少ない方法を検討します。反対に、何度も再発する・悪性の可能性が否定できないようなケースでは摘出手術を検討します。
診察のご予約はこちら
バルトリン腺嚢胞治療後の注意点
バルトリン腺嚢胞の治療後は傷口が完全に塞がっていないため、感染のリスクが高くなります。そのため、外陰部は常に清潔に保ち、排尿や排便も適切かつ十分に留意しながら行わなければなりません。
トイレットペーパーは柔らかいものを使用し、患部をゴシゴシと擦ることのないように注意します。携帯ビデなどを活用し、清潔な水やぬるま湯で洗浄すると良いでしょう。
傷口がデリケートな状態の場合、患部がしみるおそれがあるため、石鹸やボディソープの使用は避けます。ボディソープは低刺激性のものを選び、入浴は医師から許可が出るまでシャワーのみにとどめます。
治療後すぐの性行為は避け、患部に食い込むような下着の着用を控えます。開窓術の直後は1〜2週間程度、摘出手術の後は1ヶ月程度患部に刺激を加えないように注意し、期間中は医師の指示にしたがって生活してください。
自動車・自転車・バイク・椅子などに長時間座っていると、会陰部に重さが加わり負担がかかります。数日~1週間は圧迫による刺激に注意が必要です。
また、バルトリン腺嚢胞は再発しやすい疾患のため、以下のような対策が必要です。
- 通気性の良い下着を着用し、湿気や摩擦を防ぐ
- 長時間座りっぱなしの姿勢を避け、血流を妨げない
- 患部からの分泌物や違和感に注意し、異常があればすぐ病院を受診する
- 体調管理に留意し、免疫力を下げないようにして感染を避ける
抗生物質や鎮痛薬が処方されたときは、指示どおりの回数・期間にわたって服用しましょう。自己判断で中止せず、副作用が出なければすべて飲みきるようにします。
万が一副作用が出たときは、すぐにかかりつけの病院に相談してください。
バルトリン腺嚢胞は再発率が高い症状
今回は、バルトリン腺が袋状に腫れる「バルトリン腺嚢胞」の特徴や再発率、再発の原因と対処法を紹介しました。
バルトリン腺嚢胞は痛みや腫れがまったくない無症状の状態から激しい痛みや熱感を伴うものまで、さまざまな症状がみられます。無症状であっても再発を繰り返しているときは、それ以上症状が悪化しないように早期対処が必要です。
かかりつけ医と連携し、早期発見と早期対応を心がけ、患部を清潔にして予防を行いましょう。
原宿駅・渋谷駅徒歩7分の婦人科・産婦人科 LOG原宿について
診察のご予約はこちら


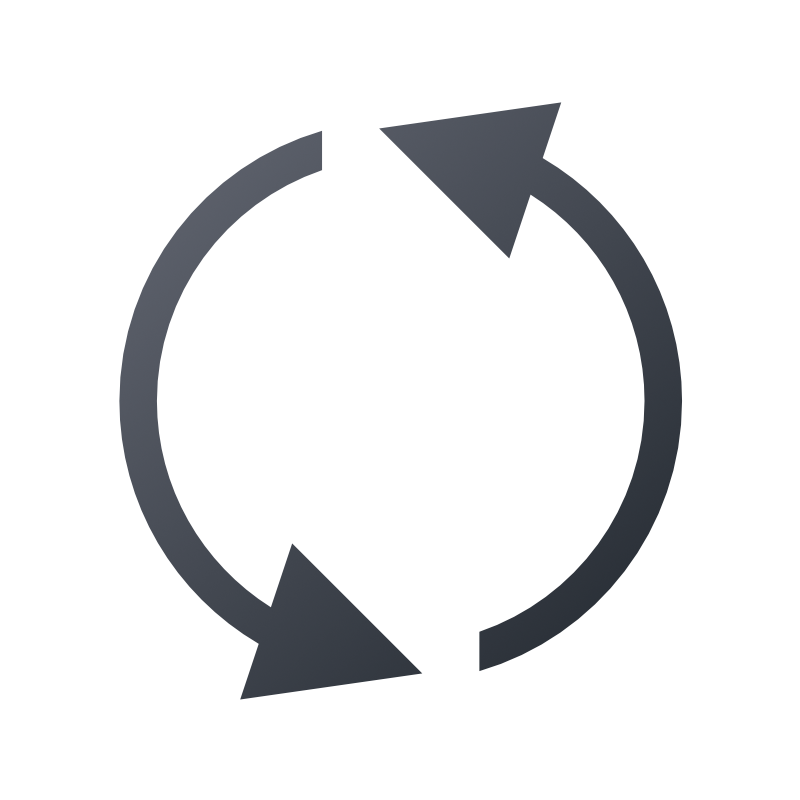 2025.11.04
2025.11.04