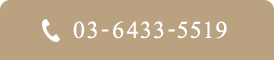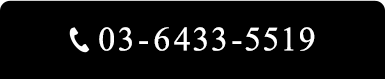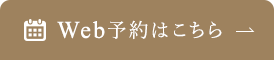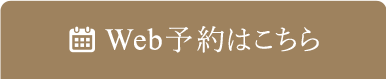コルポスコピー検査の結果はどう考えたらいいの?
コルポスコピー検査の結果、子宮頸管や膣部の組織が正常に見える場合、子宮頸がんのリスクは低いと考えられ、通常は定期的な子宮頸がん検診を継続することが推奨されます。
ただし、これは絶対的な安全を意味するわけではなく、再度、異常な細胞が検出される可能性もありますので、継続的なスクリーニングは重要です。
異常が見つかった場合、その程度によって対応が異なります。
軽度〜中等度の異常(軽度異形成)の場合、経過観察が行われます。
これは、多くの場合自然に治癒することがあるからです。しかし、高度の異形成、またはがんの疑いがある場合は、手術が行われることがあります。
コルポスコピーでは、必要に応じて生検が行われることがあります。
これにより、異形成の分類やがんの有無をより正確に判断できます。また、子宮膣部に酢酸を塗布して異常細胞をより見やすくします。
結果に関わらず、定期的なスクリーニングと医師の勧めに従うことが非常に重要です。
これにより、子宮頸がんのリスクを管理し、早期に異常を発見することができます。
子宮頚がんのリスクは、HPV(ヒトパピローマウイルス)感染、喫煙、免疫系の問題、早い年齢での性行為開始などに影響されます。
コルポスコピー検査は、これらのリスク要因を持つ女性に特に重要で、異常を早期に発見することで治療の成功率を高めることができます。

コルポスコピー検査の結果はどのぐらいで出るの?
検査の結果が出るまでには、検査の種類によって異なります。検査中に目視で異常が確認される場合、医師はその場で一定の診断を下すことができます。
しかし、もし生検(組織サンプルの採取)が行われた場合、そのサンプルは病理学的検査に送られます。
この病理学的検査の結果が出るまでの時間は、一般的に2 週間程度かかることが多いですが、施設や検査の混雑状況によってはもう少し時間がかかることもあります。
最終的な結果は、医師の診察時に説明され、必要に応じてさらなる治療計画やフォローアップのステップが決定されます。
コルポスコピー検査のページへ